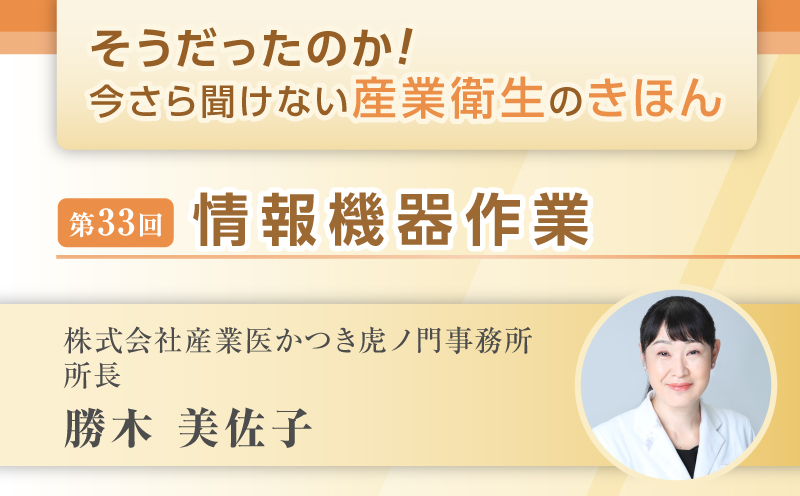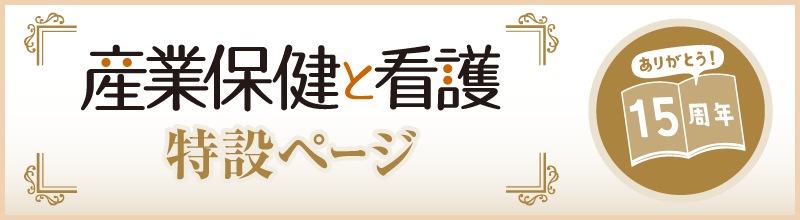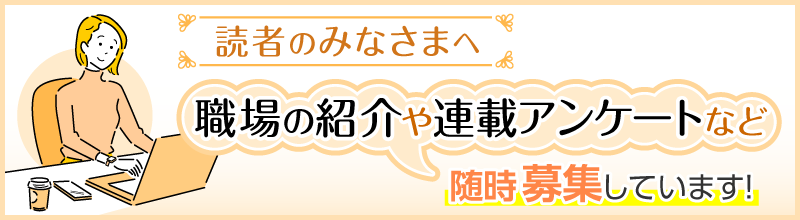あなたの会社の産業衛生は法に則り、きちんと機能していますか? ルーチンを見直すための視点をベテラン産業医が解説します。
第33回 情報機器作業
最近では、パソコンやタブレットを用いた作業が多くなっています。もちろん、これらの作業に関する労働衛生管理がガイドラインとして定められています。もともとは、2002年に「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」として策定されていましたが、VDTという用語が一般になじみがなく、またパソコンだけでなく、タブレットやスマートフォンなどの多様な機器が現場で使用されていることから、2019年に「VDT」という言葉が「情報機器」に置き換わりました。
労働衛生管理においては、3管理(本連載第2回:2017年3号)と労働衛生教育が基本となります。情報機器作業についてもガイドラインは作業環境管理・作業管理・健康管理・労働衛生教育という枠組みになっており、その他、高年齢労働者・障害を持つ作業者やテレワークに対する配慮事項が含まれています。作業環境管理では室内の照明や採光・機器の選択(ディスプレイ、キーボード、マウス)・椅子・机や騒音について、作業管理では作業時間や休憩の取り方・作業姿勢について、健康管理では健康診断・健康相談・職場体操について説明されています。衛生教育では、作業者向け(3.5時間)と管理者向け(7時間)に労働衛生教育実施要領が策定されています。
対象
1日4時間以上作業する方や、自覚症状のある方
内容
業務歴、既往歴、自覚症状の調査に加え、眼に関する調査と首や肩、手指に関する検査など
本連載は『産業保健と看護』2022年14巻4号に掲載したものを再掲載しております。
本連載へのご感想をお待ちしております。ご感想はこちら
◆著者プロフィール
勝木美佐子(株式会社産業医かつき虎ノ門事務所 所長)
平成5年日本大学医学部卒。平成8年より産業医業務開始。運送業、清掃業、製造業、地方公務員、病院、通信業、遊技業、アパレル業、IT業、ホテル業など多岐にわたる産業の産業医業務に従事。労働衛生コンサルタント、日本産業衛生学会指導医。