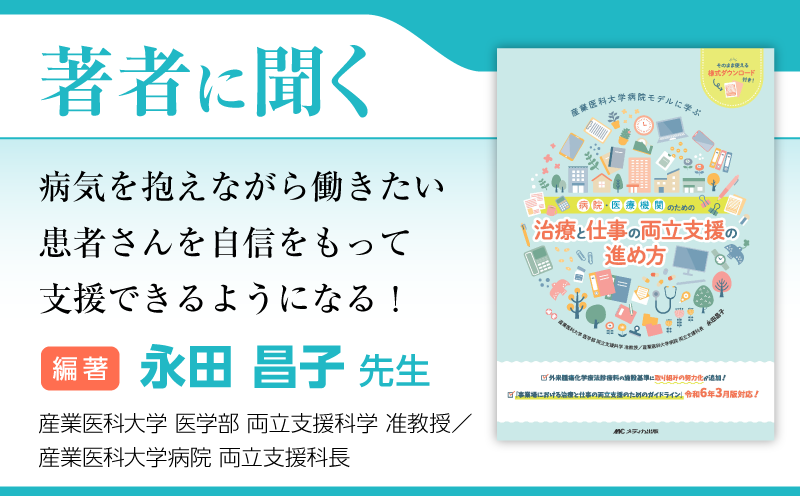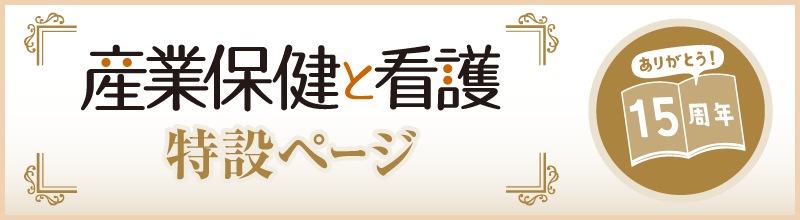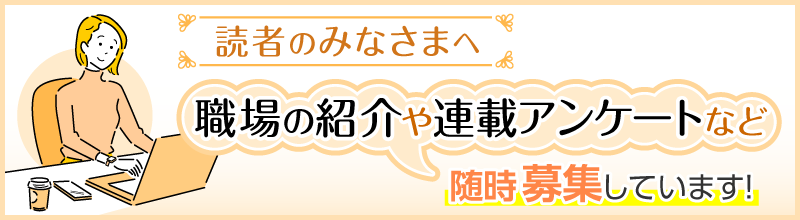病気を抱えながら仕事を続けたいと希望する人を支援するには、職場と医療機関との連携が必要です。小社刊『産業医科大学病院モデルに学ぶ 病院・医療機関のための治療と仕事の両立支援の進め方』は、病院で両立支援を始めるにあたり、何から始めてどう進めるのか、両立支援コーディネーターの活動内容や多職種連携のあり方について、産業医科大学病院での実際をもとに詳しく解説しています。編著者のお一人である永田昌子先生にお話を伺いました。(取材・構成 編集室)。
◆お話を伺った方
産業医科大学 医学部 両立支援科学 准教授
産業医科大学病院 両立支援科長
永田 昌子先生
今、さまざまな理由で治療と仕事の両立支援の取り組みが求められており、診旅報酬の仕組みなどにも新たな変更が加わっています。しかし、もともと病院というのはとても忙しいところで、治療に関して留意すべきことがたくさんあり、支援も広範囲に及ぶ中で、さらに就労支援までするというのは、医療従事者にとって、かなりチャレンジングなことだろうと思います。
就労支援をする必要性は理解できても、差し当たって何をすればよいかわからない。医療機関にとっては新たな取り組みであり、職員はみな忙しくて、そう簡単に皆の協力も得られない。そういった難しさがある中で、「産業医大はどうやっていますか?」という問い合わせを、たくさんいただくようになりました。
その中で、仕事のことは尋ねにくい。なんてアドバイスすればよいかわからない。どこと連携すればよいかわからない。どうやって始めてよいかわからない。というような多様な質問を頂戴してきました。講演や見学に来ていただいても、1時間や2時間で伝えられることにはやはり限界があります。就労に関しては、医療とは異なる視点が必要なので、短時間ではなかなか伝えきれないところがあります。そこでわれわれの取り組みをまとめた本を出版したいと考えました。
この本を読んでいただくことで、仕事のことについて安心して相談を受けることができるようになることを目指しました。
全体像が理解できるとともに多職種連携の必要性がわかる
本書では、両立支援の全体像を体系的に理解していただけるとともに、多職種連携の重要性についても深く理解していただけます。各職種がどのような役割を担い、どのように連携するのかを、実際の書式も含めて具体的に示しているため、理論だけでなく実践に即した理解が可能になっています。
例えば、ソーシャルワーカーが新たに両立支援に取り組む際、「看護師にはこのような専門的役割があります」と、具体的な根拠を示しながら他職種に協力を求めることができます。医師や事務部門に対しても、「治療と仕事の両立支援の取り組みの必要性が増している根拠はこれです」といった形で、説得力のある説明が可能です。このように、読者自身が取り組みやすく、かつ周囲を巻き込みやすいように作りました。
意見書の書き方が載っていることも特色の一つです。ソーシャルワーカーや看護師が、患者さんの困りごとを聞き、下書きを医師に渡すこともありますが、意見書に書くべき内容、留意点がわからないという場合に参考にしていただくことができるようになっています。
私の願いは、治療と仕事の両立支援に自信を持って取り組む医療機関が増えることです。これは医療従事者にとっても患者さんにとっても、非常に意義深いことだと考えています。実際に就労支援に携わる医療従事者は皆、モチベーション高く業務に取り組んでおり、患者さんとのコミュニケーションも向上しているように感じています。例えば、薬剤師であれば、従来の服薬指導に加えて就労状況についても関心を示すことで、患者さんがより積極的に相談してくださるようになります。自身の専門性が患者さんの生活全体を支えていることを実感でき、がんになっても安心して働き続けられる環境づくりに貢献できている手応えは、医療従事者にとって大きなモチベーション向上につながるのではないでしょうか。
両立支援を通じて患者さんの生活を支え、職場復帰を実現できることを実感していただければ、この取り組みは必ず日本全国の医療機関に広がっていくと確信しています。最初の一歩を踏み出すことは決して容易ではありませんが、ぜひ一歩踏み出していただきたいと願っています。

◆書誌情報
産業医科大学病院モデルに学ぶ
病院・医療機関のための治療と仕事の両立支援の進め方
- 発行 : 2025年5月刊行
- サイズ : A4判 168頁
- ISBN-13 : 978-4-8404-8814-3
- 価格 :本体5,200円+税