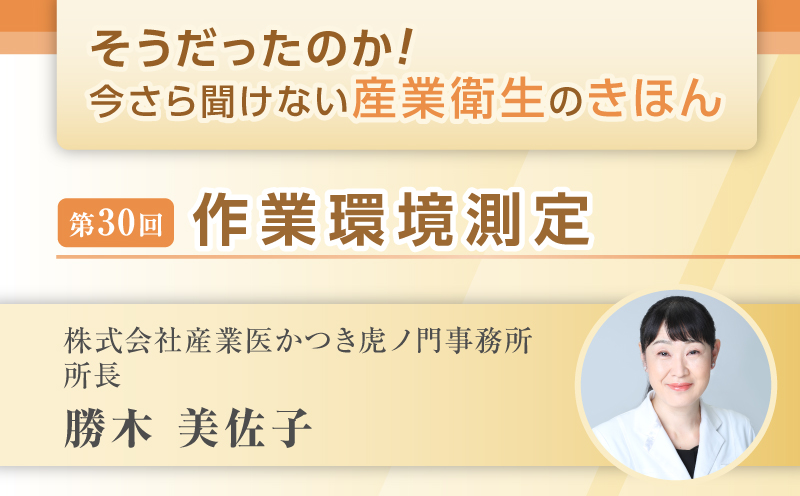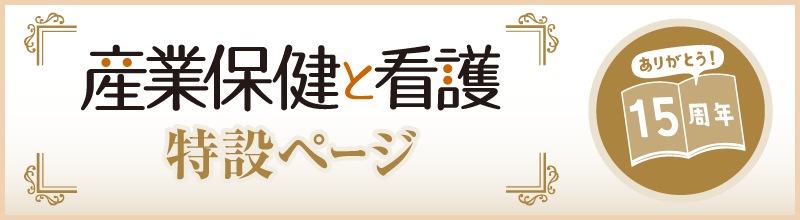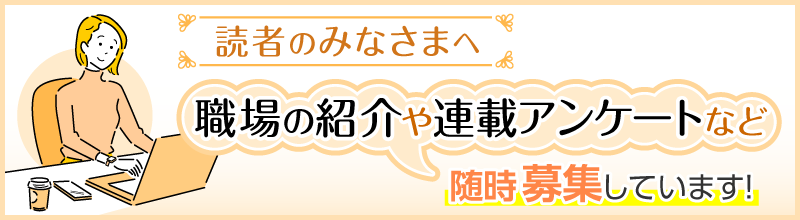あなたの会社の産業衛生は法に則り、きちんと機能していますか? ルーチンを見直すための視点をベテラン産業医が解説します。
第30回 作業環境測定
産業衛生の基本、三管理のうち「作業環境管理」の基本となるのが作業環境測定です。作業環境中に有害な因子がどのくらい存在し、労働者がどのくらいさらされているのかを測定するものです。有害な因子としては、有機溶剤、鉛、特定化学物質などの化学物質や、粉じん、電離放射線、騒音といった物理的因子などもあります。それらを把握するために、定期的に測定を行うことが法律で定められています。
測定を行った結果、有害な物質が高い場合には、封じ込めや除去を検討します。それでも低減できないようであれば、保護具などを用いて個人的な曝露を低減させ、健康障害を防止するよう対策を立てます。
作業環境測定を行う単位作業場所は、作業者の行動範囲と有害物質の分布状況で決めます。A測定(平均的な状態を把握するための測定)とB測定(有害物質の濃度が最も高くなると思われる時間・位置での測定)の結果をもとに、作業環境、作業(手順・保護具)、特定健康診断の結果確認までの流れに沿って確認してみましょう。
粉じん、有機溶剤などは法定回数を測定し結果を法定年数保存する
2 安衛法第65条第2項
作業環境測定基準に従って測定する
3 作業環境測定法第3条
特定の指定作業場は、作業環境測定士が測定する必要がある
本連載は『産業保健と看護』2022年14巻1号に掲載したものを再掲載しております。
本連載へのご感想をお待ちしております。ご感想はこちら
◆著者プロフィール
勝木美佐子(株式会社産業医かつき虎ノ門事務所 所長)
平成5年日本大学医学部卒。平成8年より産業医業務開始。運送業、清掃業、製造業、地方公務員、病院、通信業、遊技業、アパレル業、IT業、ホテル業など多岐にわたる産業の産業医業務に従事。労働衛生コンサルタント、日本産業衛生学会指導医。