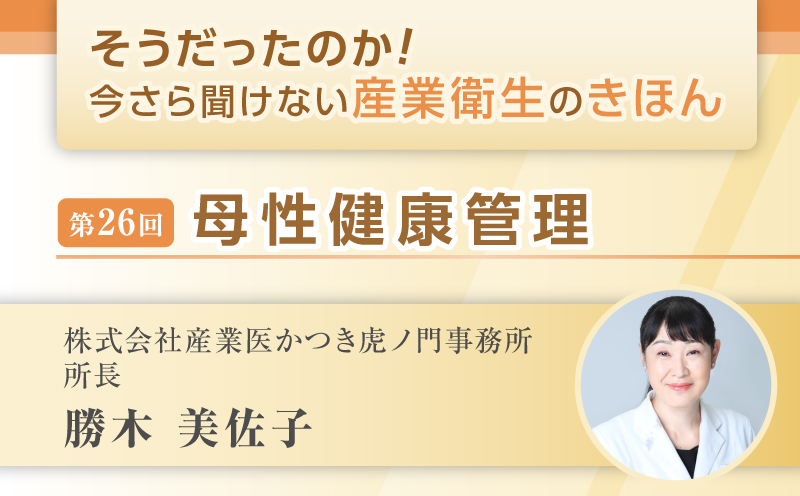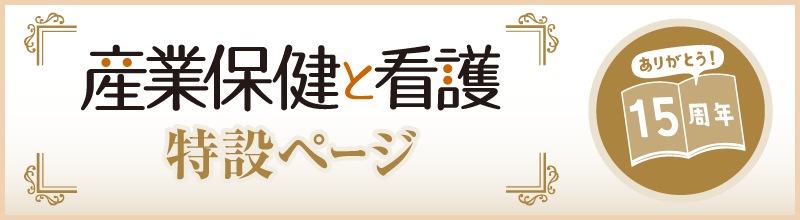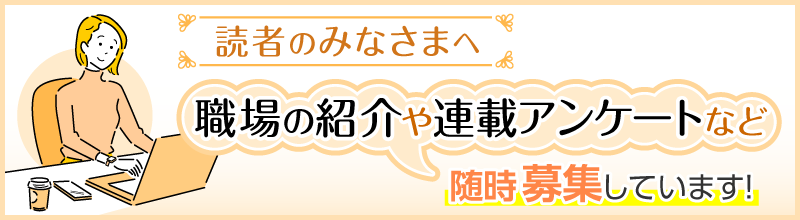あなたの会社の産業衛生は法に則り、きちんと機能していますか? ルーチンを見直すための視点をベテラン産業医が解説します。
第26回 母性健康管理
新型コロナウイルス感染症拡大に伴って新しい働き方が定着しつつありますが、それでも働く妊婦さんにとっては、依然として通勤や環境に不安が多いと思います。今回は、働く女性が安心して、妊娠・出産・育児ができるような規定である「母性健康管理」についてお話しします。今までのコラムでは、ほとんどが労働安全衛生法を基づくものでしたが、母性健康管理は労働基準法と男女雇用機会均等法による管理になります。
労働基準法では、母性を保護するために①産前・産後休業、②妊婦の軽易業務転換、③妊産婦等の危険有害業務の就業制限、④妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限、⑤妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限、⑥育児時間が規定されています。これらのうち、産後休業と危険有害業務の就業制限以外は、本人からの請求があった場合とされています。
また、請求したことで不利益な取り扱いを受けないように、男女雇用機会均等法に定められています。男女雇用機会均等法では、ほかに①保健指導や健康診査を受けるための時間の確保、②指導事項を守るようにするための措置を定めています。
かかりつけの医師からの指導事項がスムーズに事業所に伝わるよう、「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」もあります。カードが提出されたら、スムーズに配慮できるよう、調整を行っていきましょう。
本連載は『産業保健と看護』2021年13巻3号に掲載したものを再掲載しております。
本連載へのご感想をお待ちしております。ご感想はこちら
◆著者プロフィール
勝木美佐子(株式会社産業医かつき虎ノ門事務所 所長)
平成5年日本大学医学部卒。平成8年より産業医業務開始。運送業、清掃業、製造業、地方公務員、病院、通信業、遊技業、アパレル業、IT業、ホテル業など多岐にわたる産業の産業医業務に従事。労働衛生コンサルタント、日本産業衛生学会指導医。