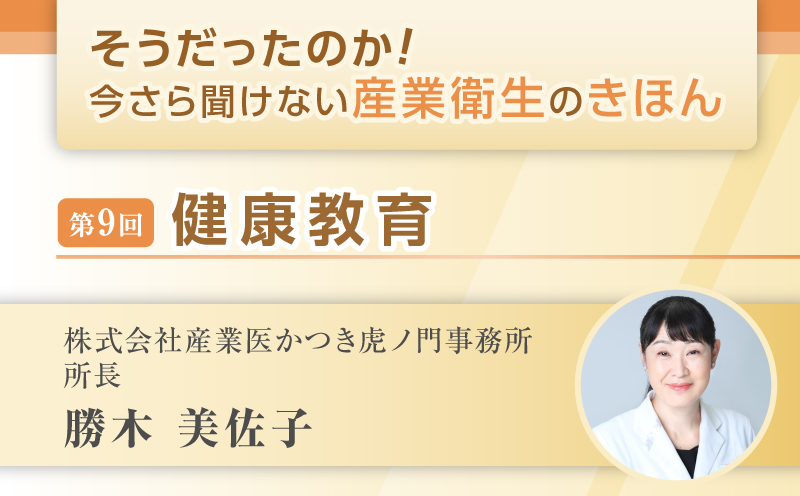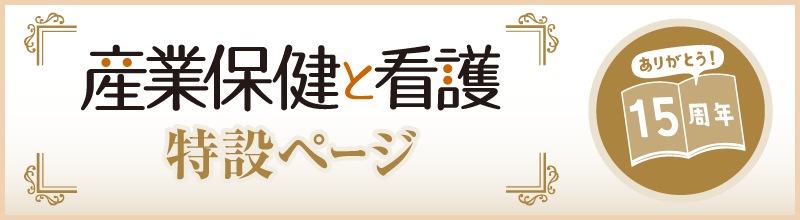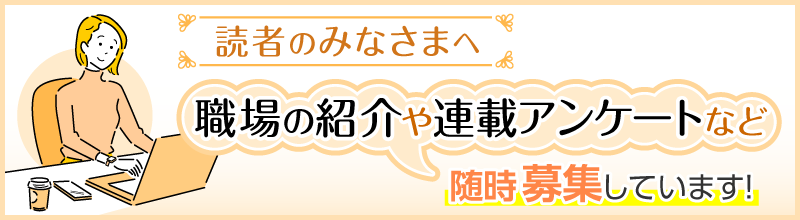あなたの会社の産業衛生は法に則り、きちんと機能していますか? ルーチンを見直すための視点をベテラン産業医が解説します。
第9回 健康教育
前回のお話は、個人に対してのアプローチ(ハイリスクアプローチ)である保健指導でした。
今回は、集団に対してのアプローチ(ポピュレーションアプローチ)である健康教育についてお話しします。
産業保健での「健康教育」は労働安全衛生法第69条に基づくものです。ほかにも、雇い入れ時の安全衛生教育(同法第59条第1項)、作業変更時の安全衛生教育(同法第59条2項)などがあります。
安衛法69条には、健康教育を継続的かつ計画的に行うことと規定されています(下図参照)。
■事業者は、労働者に対する健康教育および健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
計画的に行うために、年度初めの衛生委員会で、その年の通年のテーマを決める方法もありますし、毎月異なるテーマ(夏場の熱中症対策、冬場のインフルエンザやノロウィルスの予防など)を決めて、そのテーマの資料を衛生委員会や朝礼で配布したり、ポスターを掲示したりする方法があります。
雇い入れ時の健康教育で、健康診断の受診義務について説明すると、受診率アップにつながります。また、健康診断で有所見の多かった項目や、保健指導中に頻繁に見られた不健康生活(朝食の欠食、運動不足など)についてテーマにするのもいいでしょう。健診受診率や、健康診断有所見率などが、評価の指標になります。
ぜひ年度初めに健康教育の計画を立てて、評価し、翌年度の改善へと、PDCAサイクルを活用して継続的に行ってみてください。
本連載は『産業保健と看護』2018年10巻4号に掲載したものを再掲載しております。
本連載へのご感想をお待ちしております。ご感想はこちら
◆著者プロフィール
勝木美佐子(株式会社産業医かつき虎ノ門事務所 所長)
平成5年日本大学医学部卒。平成8年より産業医業務開始。運送業、清掃業、製造業、地方公務員、病院、通信業、遊技業、アパレル業、IT業、ホテル業など多岐にわたる産業の産業医業務に従事。労働衛生コンサルタント、日本産業衛生学会指導医。