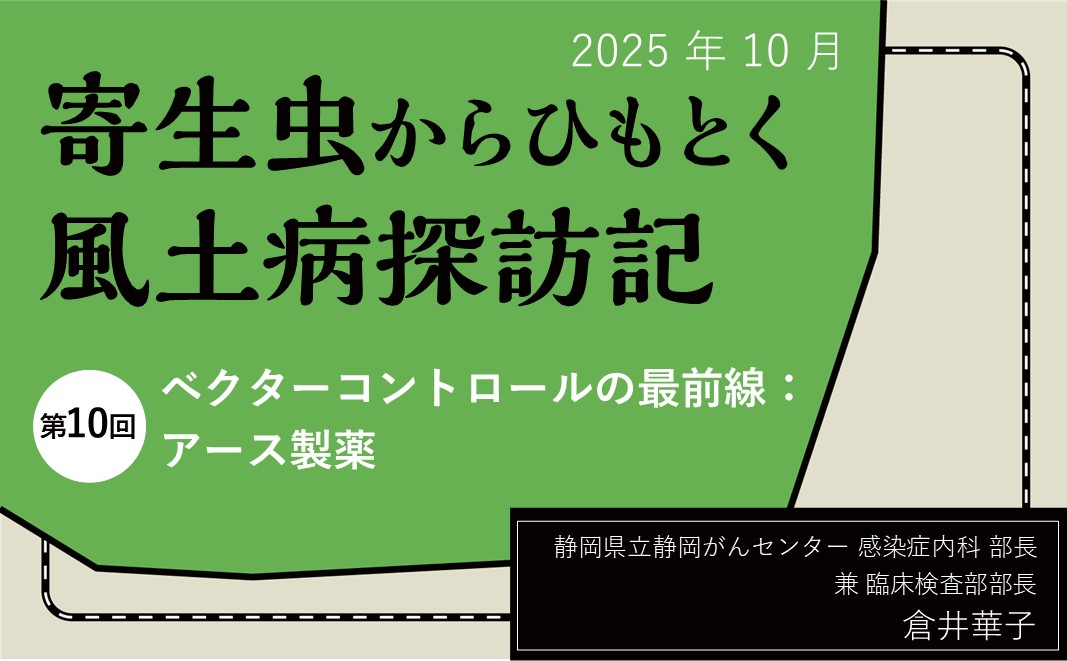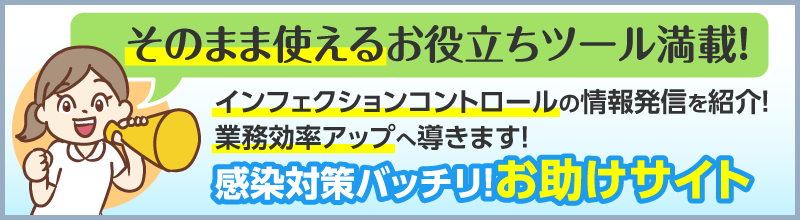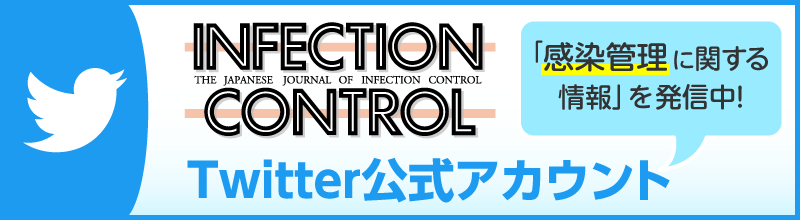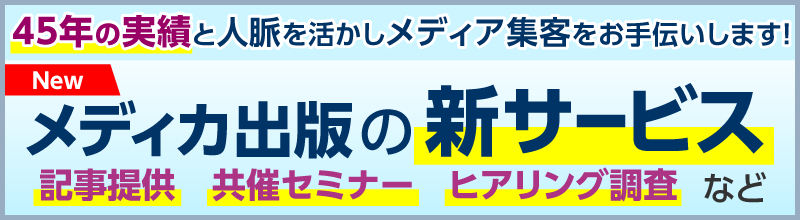第10回 ベクターコントロールの最前線:アース製薬
*本連載は2019年1月号~12月号の本誌連載の再掲載記事になります。
*本記事の無断引用・転載を禁じます。
マラリアや日本紅斑熱など、蚊やダニを媒介して感染する疾患は多い。蚊やダニを地球上からすべて駆除するのは困難であり、私たちの居住区域にこれらの動物を入れないこと、彼らの居住地に私たちが入るときには防御をする必要がある(筆者は個人的趣味として蚊に刺されることが好きなので、我が家はノーガードである)。
いざ、アース製薬の研究所へ!
アース製薬は1900年代初期から殺虫剤を製造し、現在もさまざまな製剤を研究開発している。ちなみに2017年からは「殺虫剤」の呼び名を「虫ケア用品」に変更しており、虫に優しいイメージで私にとってはうれしい変更であった。
そんなアース製薬の研究所が兵庫県赤穂市にある。ゴキブリ100万匹、蚊とハエで10万匹を飼育するというこの日本一の研究施設に、今回お邪魔した。案内していただいたのは「きらいになれない害虫図鑑(幻冬舎)」の作者でもある、ゴキブリ女子仲間の有吉立さんである。有吉さんは研究所のすべての虫たちの世話をしている、“害虫のプロ”である。
「ゴキブリの部屋」と殺虫剤耐性
今回は飼育室の隅から隅まで見せていただいた。なんといっても圧巻なのは数十万匹のワモンゴキブリを放し飼いにしている“ゴキブリ部屋”である(写真でお見せできないのが残念だ)。筆者は喜んで部屋に入ったが、部屋に入ったとたんにゴキブリたちがサーっと逃げていき、その物音がすごかった。ゴキブリたちも本当は人間を怖がっていることが実感できた。
筆者のゴキブリ愛だけで原稿が終わりそうだが、ベクターコントロールという点からゴキブリの殺虫剤耐性についても述べる。飲食店などで見かけるチャバネゴキブリは、殺虫剤の主成分として用いられているピレスロイド系薬剤に耐性を有してきている。こうした耐性に対してもアース製薬ではさまざまな薬剤の開発に力を入れている。
「蚊の部屋」と忌避剤のパワー
もう一つのメインである、“蚊の部屋”も見せていただいた。デング熱などを媒介するヒトスジシマカとアカイエカが主に数多く飼育されていた。卵から幼虫、蛹、そして成虫と早いサイクルで成長するため、毎日のお世話が欠かせない手のかかる虫たちである。
蚊の忌避剤としてはディート(ジエチルトルアミド)やイカリジンなどが用いられる。ディートは濃度が高いほど効果時間が持続するとされる。今回は特別に、蚊の忌避剤の効果について実験させていただいた。ぜひ写真2と3を見比べていただきたい。正直なところ筆者が虫ケア用品を使用したのは実に十数年ぶりだったが、ここまで効果が明らかになるとは思わなかった。まんべんなく忌避剤を塗り広げた後では、蚊は近寄らないか、手に止まっても吸血をしてくれない…!

写真2 忌避剤塗布前(アカイエカ)

写真3 忌避剤塗布後(アカイエカ)
忌避剤を塗るポイントとしては、十分な量を使用しまんべんなく塗り広げること(筆者は両腕に塗るだけで数十秒かかった)、効果時間に応じこまめに塗りなおすことが重要である。
蚊やダニの居住区にお邪魔する際は、身を守るために、自己責任としてこうした忌避剤を使用することが節足動物外界感染症の防護にもつながることを学んだ。
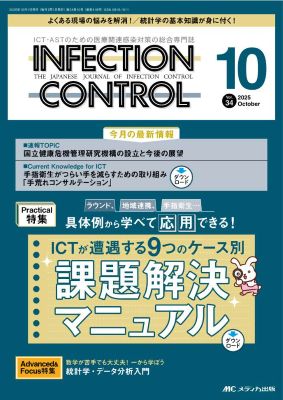
⇧最新情報は こちら から