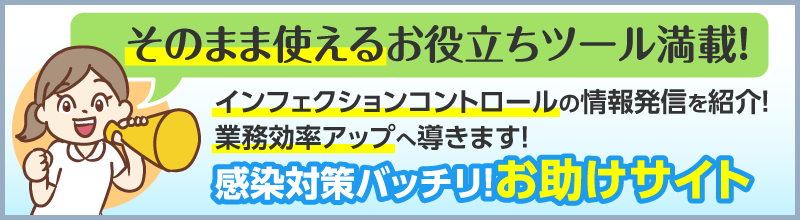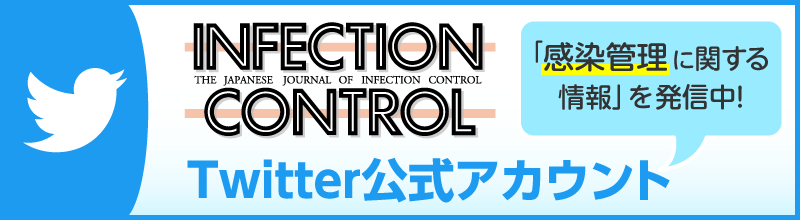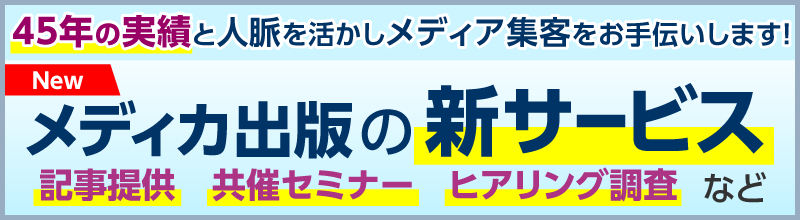矢野邦夫先生に「透析施設におけるCandida aurisの封じ込め対策」についてご執筆いただきましたので、掲載いたします。
*INFECTION CONTROL34巻11月号の掲載の先行公開記事となります。
「透析施設におけるCandida aurisの封じ込め対策」
CDC が血液透析施設におけるCandida auris対策の現状と課題について述べているので紹介する[https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/74/wr/pdfs/mm7423a2-H.pdf]。
Candida auris
Candida auris (以下、C. auris) は、多剤耐性真菌であり、医療施設内での急速な拡散能力を有し、公衆衛生上の緊急の脅威となっている。C. auris感染症の約39%が致命的であると推定されており、治療選択肢も限られている。特に、末期腎疾患患者は、重篤な基礎疾患、免疫不全状態、侵襲的な医療機器の使用、広域抗菌薬の頻繁な投与などにより、C. aurisの保菌または発症に対するリスクが高い。CDCは、2020~2023年にかけてC. auris保菌例または発症例が確認された透析関連5施設(4州)を対象とした感染対策の実態を分析した。
調査概要
調査対象は、ニュージャージー州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、テネシー州の4州に所在する5つの医療施設である。各施設では、C. auris陽性患者が透析を受けていた事例が確認され、そのうち5例では透析施設側が患者の保菌や発症状況を把握していなかった。これに対して州保健局が主導し、接触者への保菌検査(合計174人)、感染対策の評価、指導などが実施された。
症例定義
「保菌症例」は施設内でのサーベイランス活動の一環として採取された腋窩、鼠径部、鼻腔のスワブ検体のPCR検査または培養検査によって、透析患者からC.aurisが検出された場合と定義された。「発症症例」は施設内で透析を受けている患者から、臨床ケアの一環として採取された検体からC. aurisが検出された場合と定義された。
感染対策の効果
注目すべきは、C. auris特有の対策が導入されていない段階でも、透析施設の標準的な感染対策により、二次感染は確認されなかったことである。感染対策には、手指衛生、個人防護具(personal protective equipment, PPE)の交換、ベッドユニットの清拭・消毒、物品の個別使用・管理などが含まれる。また、米国環境保護庁が指定する消毒薬の使用が推奨されていた。
感染対策上の大きな障壁
本調査では、施設間および州間の情報共有の欠如が課題として浮上した。特に、急性期病院から透析施設へのC. auris陽性情報の未通知、感染対策担当者の不在、高い職員離職率などが、保菌検査や封じ込め対策の遅延を引き起こしていた。テネシー州では、既知の陽性患者が透析導入されたにもかかわらず、情報が施設側に伝達されていなかった事例が報告されている。
患者の受け入れ拒否と誤解
一部の透析施設では、C. auris陽性患者の受け入れに対して消極的な姿勢がみられた。その理由として、共用スペースでの透析、隔離室の不足、他患者への曝露リスクがあげられた。しかし、CDCはC. auris陽性患者の透析に隔離室を必要としない方針を示しており、PPEや清拭・消毒の徹底、時間帯調整(最終シフトでの透析)などで対応可能であると強調している。
公衆衛生上の示唆
本報告は、透析室の標準的な感染対策の徹底によって、C. auris陽性患者に対する安全な透析が可能であることを示唆している。一方で、感染対策の実効性を確保するためには、施設間連携の強化、特に患者移送時の感染状況に関する即時共有が不可欠である。今後は、透析環境におけるC. aurisの保菌率や伝播リスク因子の解明に向けたさらなる研究が求められる。
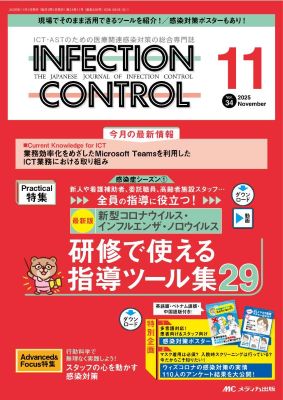
(本誌のご購入はこちらから)
*INFECTION CONTROL34巻11月号の掲載の先行公開記事となります。
*本記事の無断引用・転載を禁じます。