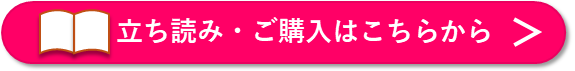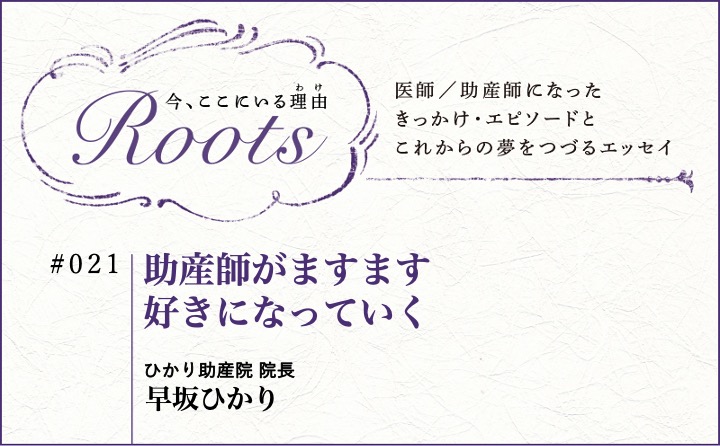早坂ひかり
1960年、私が生まれたこの年は、ちょうど施設内出産が自宅出産を上回った時期でもある。助産学生に「私は自宅で生まれた」と話すと、多くの学生があっけにとられた表情を見せる。学生たちにとって私は「遠い昔に生まれた人」というイメージであろうか。私が生まれた香川県宇多津町では、当時、町のほとんどの出産を産婆さんが担っていたようだ。私の名前も産婆さんが付けてくれたと母から聞いている。それほど助産師と家庭との距離が近かったのだろう。
助産師を目指したことに、強い動機があったわけではなかった。ただ、折に触れて母から「手に職をつけなさい」と言われて育ったことや、看護学実習で唯一「おめでとうございます」と言える場所が産科病棟だったということくらいである。助産学生時代は「こんな高度な仕事は私にはとても無理だ」と何度も辞めようと思った。しかし、その中でも助産学の講義で「お産は正常なら待つことが大原則です」と教わったことは今でもはっきりと覚えている。
助産学校を卒業後は病院勤務を経て、その後の約20年間は看護基礎教育に携わった。看護学を教えること以上に、職業人として人を育てるということの難しさを日々痛感する教員生活だった。今振り返れば、苦しくも楽しい日々であり、私自身を人として成長させてくれた経験だったと思う。
50歳を迎える頃、助産師として母子に直接寄り添える環境のもとで働きたいと思い、教員を辞めて近所でお産を扱う『とも子助産院』に就職した。助産学生時代に教わった「正常なら待つ」というお産の大原則を実践できる助産院での日々に心から幸せを感じた。
3年後に『ひかり助産院』を開業し、地域の助産師として仕事をするようになってから、かつての教え子が訪ねてくることがある。助産院で出産してくれた教え子や、産後ケアに来てくれた教え子もいる。教え子が出産して母親となり、育児に励む姿はまぶしく、助産師を続けてきてよかったと心から思える瞬間の一つである。年齢を重ねるにつれて、私は助産師という仕事がますます好きになっている。これからも力が続く限り、愛しい赤ちゃんと母親たちのために、地に足をつけて働き続けていきたい。
本記事は『ペリネイタルケア』2025年10月号の連載Rootsからの再掲載です。
➡︎連載「姿勢と呼吸をととのえるガスケアプローチ」の動画はこちらから