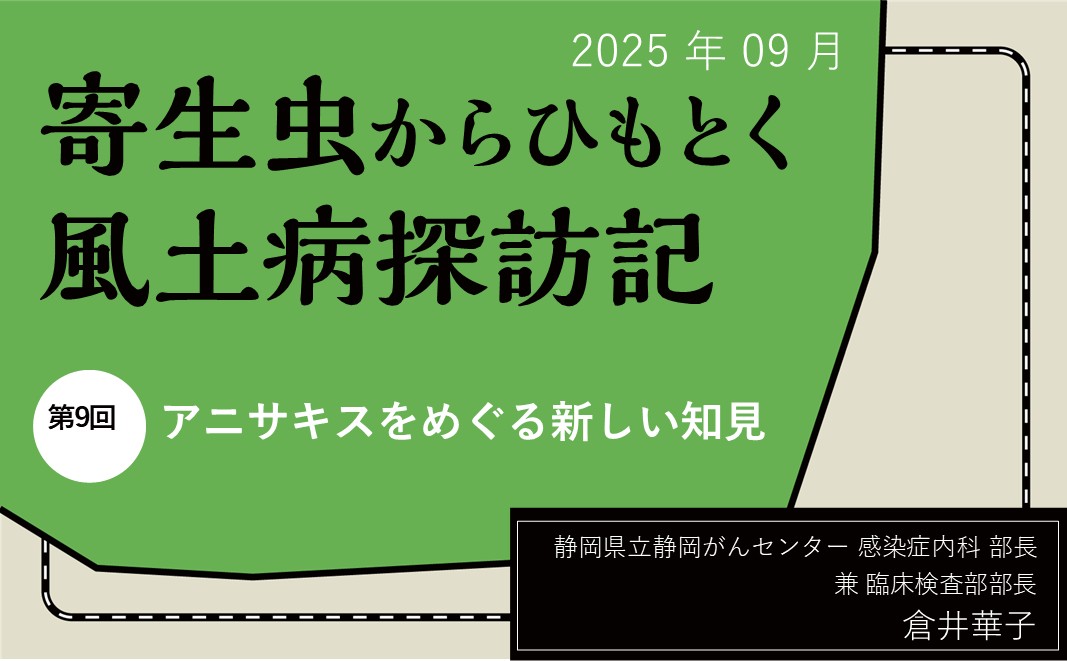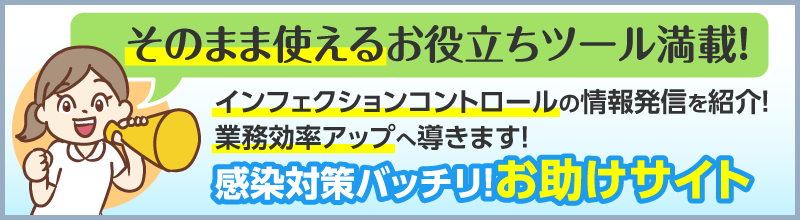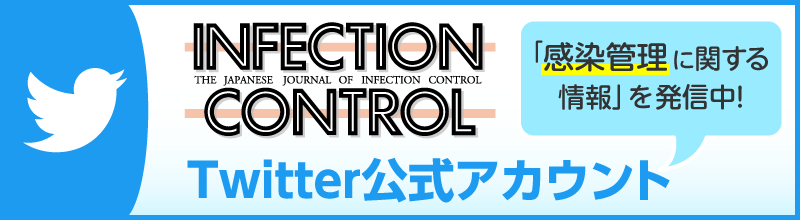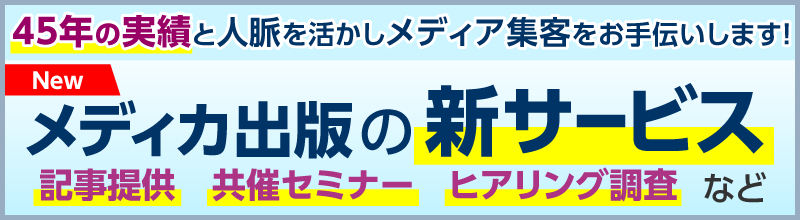第9回 アニサキスをめぐる新しい知見
*本連載は2019年1月号~12月号の本誌連載の再掲載記事になります。
*本記事の無断引用・転載を禁じます。
患者の特徴
45歳男性、就寝中に突き刺すような心窩部痛と悪心が突然出現し、救急外来を受診した。夕食には家庭で調理したしめ鯖を食べている。
さてどのような病原体が考えられるか?
◎答え:アニサキス
摂食歴が聴取できて、潜伏期(摂食後1時間から長くて4日間)と併せて考えれば、本疾患を疑うことは比較的容易であろう。内視鏡検査を行い、鉗子で幼虫を摘出すれば速やかに症状が改善する(図1)。アニサキスはアニサキス亜科線虫の総称である。中間宿主はオキアミで、イカやアジなどの魚は待機宿主となる。イルカクジラ、アザラシなどの海洋に生息する哺乳類を終宿主(アニサキスが成虫になることができる宿主)とする。ヒトも待機宿主となるわけだが、アニサキスにとっては望まない終わり方である(筆者は消化管のアニサキスを見るとひそかに涙している)。

図1 人の胃内のアニサキス(泣)
アニサキスアレルギー
ヒトに対する影響は、アニサキスが胃や腸に寄生して起こる「消化管アニサキス症」が有名であるが、近年「アニサキスアレルギー」も知られるようになった。魚に寄生したアニサキスが抗原となり、蕁麻疹や顔面浮腫、アナフィラキシーなどの即時型アレルギー反応が起こる。アニサキスアレルギーは生きた虫体によるものだけではなく、冷凍や加熱処理によって虫体が死んだ状態であっても起こる。今まで“青魚アレルギー”として考えられていた疾患の大部分が、本疾患であることが分かってきた。
アニサキスの統計
今回は消化管のアニサキス症について、杉山広先生(国立感染症研究所寄生動物部)にお話を伺った。国内では2012年の食品衛生法の一部改訂により、2013年以降、食中毒統計からアニサキス症の発生数を見られるようになった。年間100〜500例のアニサキス症が報告されており、ここ1〜2年は増加している(表1)[1]。ただし、国内での実際の患者数は毎年7,000人と推定されており、報告されていない症例はまだまだ多いと考えられる。アニサキス症を見た場合には食中毒として届出が必要であることが、いまだ認識されていないのが問題である。
表1 食中毒統計に基づく患者数
| 年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 患者数 | 89 | 79 | 133 | 126 | 230 | 468 |
(文献1より作成)
遺伝子解析によるアニサキス症の新しい知見
近年遺伝子解析が進み、ヒトのアニサキス症について分かってきたことも多い。
魚介類に寄生するアニサキスの種類は、魚種や魚の生息海域、生息深度などによって異なる。なかでも、ヒトのアニサキス症に関わる種類にはAnisakis simplexが多いことがかつてより知られていた。近年の研究では、このAnisakis simplexがさらに「Anisakis pegreffii(アニサキス・ピグレフィー),Anisakis simplex sensu stricto(アニサキス・シンプレックス・センス・ストリクト),Anisakis berlandi」の3種に分類されることが分かった。おもしろいことに、国内のアニサキス症患者から検出した虫体を調べると、96%がアニサキス・シンプレックス・センス・ストリクト(舌を噛みそう)である。アニサキス・シンプレックス・センス・ストリクトはアニサキス・ピグレフィーと比べ100倍ほど魚の筋肉への移行率が高いようであり、この性質は感染者数に影響していると考えられる。
アニサキス症の原因となる魚はサバが多い。同じマサバであっても日本海側のマサバにはアニサキス・ピグレフィーが寄生しており、太平洋系群のマサバにはアニサキス・シンプレックス・センス・ストリクトが寄生することも分かった。太平洋側のマサバを狙うほうが、アニサキス症にかかりやすいといえるかもしれない。
臨床情報、魚の調査、遺伝子解析などの情報を重ねることにより、近年アニサキス症でさまざまな新たな発見がされている。症例を見たら届出を!
●文献
1)厚生労働省.4.食中毒統計資料.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html
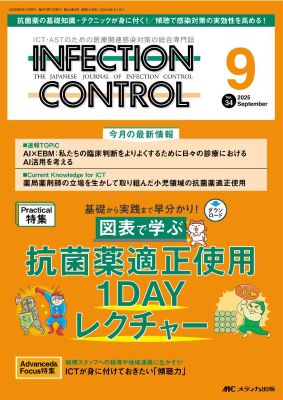
⇧最新情報は こちら から