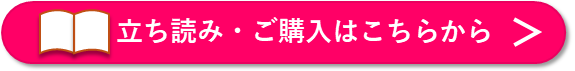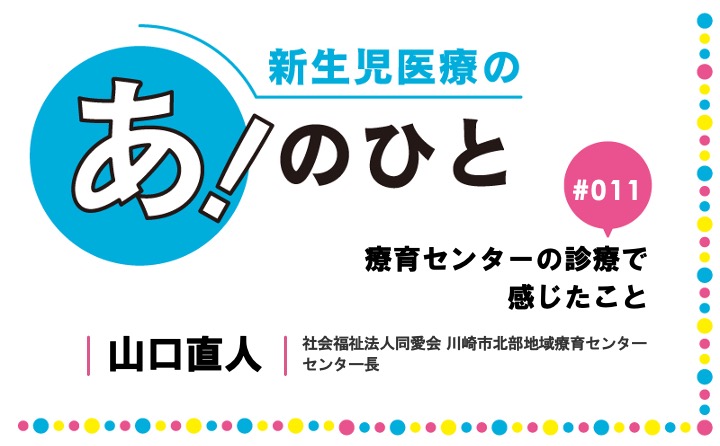療育センターの診療で感じたこと
私は5年ほど新生児医療に従事した後、もともと少し興味のあった療育センターで10年ほど働いています。当初はちょっと学んで新生児科医に戻るつもりでしたが、今は子どもと家族が健やかに育つシステムの複雑さを学ぶのにはまだまだ時間がかかると感じています。本稿では、EBM(evidence-based medicine)や教科書の世界を離れ、療育センターの臨床から個人的に感じていることを少し漏らしてみようと思います。
そのうちの一つは、医療的な介入をシンプルにする努力を続けることが必要だということです。訪問診療・訪問看護などが広まり、地域によっては高度な医療を続けながら家庭で暮らす子どもが増えています。だいぶ手厚い1:1、時にはそれ以上の看護体制を出せる家庭の力(愛情ともいう)の影響で、ケアはシンプルになっているというよりも、個別性・複雑性を増す傾向があるようで、時に医療機関以上と感じることがあるほどです。
療育センターや学校の支援では、家庭生活への援助も行いますが、子どもの発達に必要な、家庭の外で活動する経験をより豊かに増やすことを中心にしています。医療的な介入は、体調を安定させて活動に参加する機会を作る一方で、活動や集中を中断する存在にもなり得ます。しかも、看護体制は家庭や病院のハイケア病床に及ばない場面が少なくありません(特に筆者が勤めた短期入所の施設は10:1 の看護体制で、難しいことばかりでした)。もちろん全国で取り組まれているような体制整備が進むことはとても重要ですが、医療チームが安全を保証しながら医療的な介入をシンプルにする小さな努力を続けることで、保育や教育の現場に時間と人手と安全が増え、子どもたちの経験がより豊かに広がる可能性があると考えています。
とはいえ、診療場面で、保育施設や学校に合わせた医療的な介入を考え、指示を工夫するのは簡単とはいえません。そのために連携する時間や機会は足りず、家族や現場に任せた方が良いと考えるけれど、現場では医師の指示が思った以上に重要で……と板挟みになっているような気持ちになるかもしれません。
そこでおすすめしたいのは、療育施設や学校で勤務してみることです。訪問診療というライバルができたためか? 以前にも増して療育施設の医師不足が進んだ地域もあるようです。保育や教育、リハビリテーションの現場にお邪魔して現場のスタッフや子どもたちと直接やりとりする経験は、診察室での相談対応の幅を大きく広げることでしょう。ぜひ!!
社会福祉法人同愛会 川崎市北部地域療育センター
センター長
山口直人
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
す!がおのひとこと
国際認定ラクテーション・コンサルタント(IBCLC)の仕事を続けています。母乳育児支援の現場で直接支援する機会は少なくなりましたが、親としての初期の営みを直接支援するスキルは、他の育児支援や診療場面で大変役立っています。ぜひ一緒に学びましょう! 写真は、改訂された教科書『母乳育児支援スタンダード』です。NICUに関する部分の執筆は、私から新藤潤先生(東京都立小児総合医療センター)に代わり充実した内容です。おすすめです!!!
本記事は『with NEO』2025年5号の連載「新生児医療の あ!のひと」からの再掲載です。