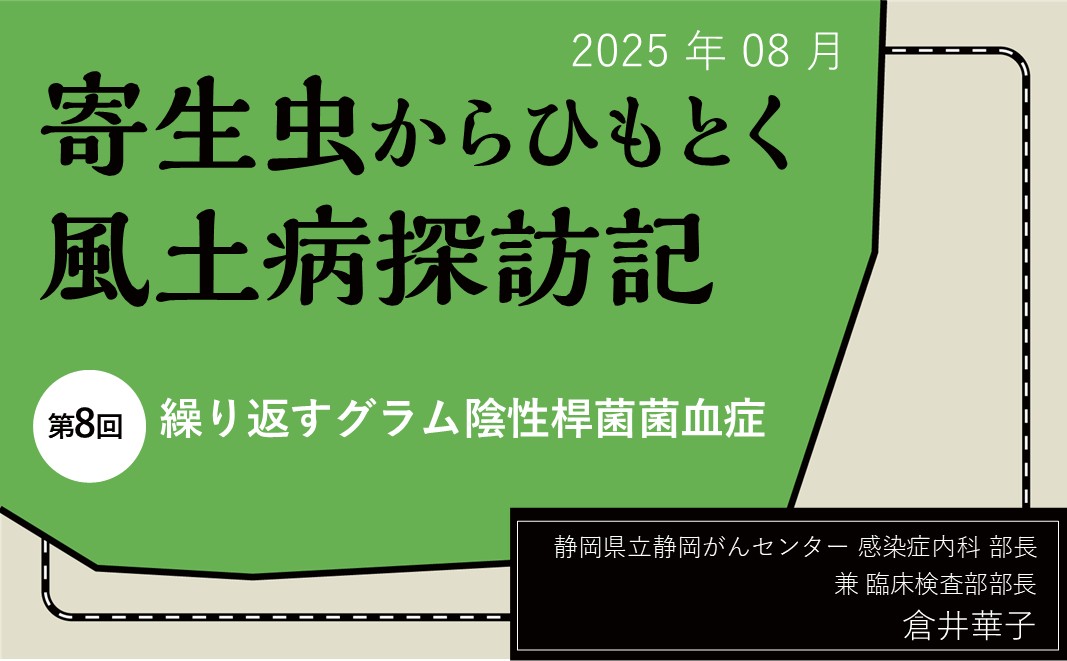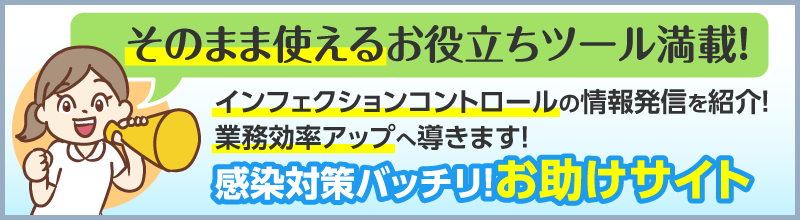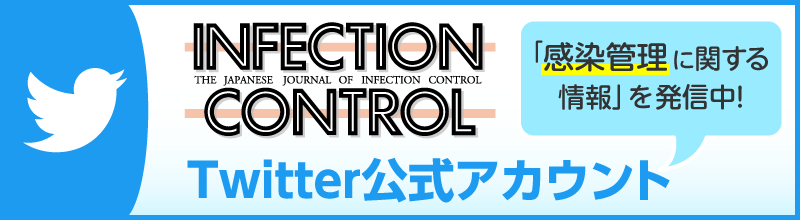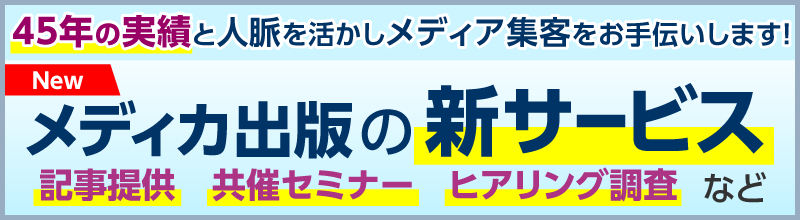第8回 繰り返すグラム陰性桿菌菌血症
*本連載は2019年1月号~12月号の本誌連載の再掲載記事になります。
*本記事の無断引用・転載を禁じます。
患者の特徴
72歳女性。発熱、頭痛、意識障害で緊急入院。身体診察で体温38.4℃、意識レベルJCSⅠ-3。項部硬直あり。腰椎穿刺で好中球増加と糖低下があり髄膜炎と診断。セフトリアキソン+バンコマイシンで治療を開始。翌日血液培養と髄液培養でグラム陰性桿菌が陽性となった。慢性関節リウマチで長期ステロイドを使用している。結婚前は奄美諸島に住んでいた。
さてどのような病原体が考えられるか?
◎答え:糞線虫症
糞線虫症とは、糞線虫(Strongyloides stercoralis)よって引き起こされる寄生虫疾患である。糞線虫症は、土壌から経皮的にヒトに感染し、主として十二指腸や小腸上部の粘膜に寄生する(図1)。自覚症状のない症例、腹痛・腹鳴・軟便などの消化器症状を認める軽症例が大半であるが、ときに提示症例のような重症例も経験する。重症例は何らかの免疫能の低下を背景に持つ例が多い。免疫不全患者では腸管から自家感染したフィラリア型幼虫が全身に散布される。糞線虫の移動とともに腸内細菌が血流や全身臓器に播種され、敗血症、肺炎、化膿性髄膜炎などを合併し重症化する。

図1 糞便より検出した糞線虫
糞線虫は東南アジアを中心とする熱帯から亜熱帯地域を中心に幅広い地域に生息し、国内では沖縄や奄美群島に多い。沖縄は古くから知られた糞線虫症の流行地であり、かつては住民の20%以上に感染が認められるような地域も多数あったという。また、沖縄は成人T細胞白血病(ATL)の多発地城でもあった。ATLの原因はヒトT細胞白血病ウイルス1型(Human T-cell leukemia virus type1,HTLV-1)であり、母子感染が主な感染経路として知られている。この2つの疾患の関連性については、現在は一般的知識となっているが、その関連について初めて世界に報告したのは沖縄の小さな診療所で働く医師であった。今回はその報告者である、沖縄医療生活協同組合沖縄協同病院の仲田精伸(なかだきよのぶ)先生にお話を伺った。
重症化因子の解析
仲田先生は1984年にLancetへこの報告を出している[1]。仲田先生は糸満診療所で多くの糞線虫症を治療していたが、重症の糞線虫症ののちに白血病やリンパ腫を発症した症例を2例経験し、通常とは異なる感覚を抱いたという。患者を調べていくと糞線虫保有者はその半数以上が、抗HTLV-1体陽性が陽性であることが分かった。その後HTLV-1の研究者たちと協力し、沖縄での糞線虫の基礎疾患、および重症化因子がHTLV-1であることを明らかにした。
糞線虫は一度罹患すると数十年にわたり持続感染が起こりうる。HTLV-1の患者では自覚症状がなくとも、くすぶり型ATLを発症している場合もある。免疫不全に伴い糞線虫が増殖し、重篤な糞線虫感染症を発症すると推測されている。HTLV-1キャリアでは母乳を介した子へ感染が主な感染経路であり、妊婦教育で感染を防ぐことができる。市民教育や衛生環境の改善とともに、沖縄では徐々にHTLV-1キャリアも、重症糞線虫患者も減少している。
小さな気付き
仲田先生は語る、「日常診療のなかに問題解決のヒントがある、今後日本以外でも糞線虫とHTLV-1の関連を証明していってほしい」と。診療でも感染対策でも、「小さな気付き」が重要であり、通常と違う事象をうまく拾い上げ問題解決につなげる力が求められる。おかしいと思う感覚を鈍らせず、つねに疑問を持ち続ける姿勢を私も持ち続けたい。
●文献
1) Nakada,K.etal.High incidence of HTLV antibody in carriers of Strongyloides stercoralis.Lancet.1(8377),1984,633.
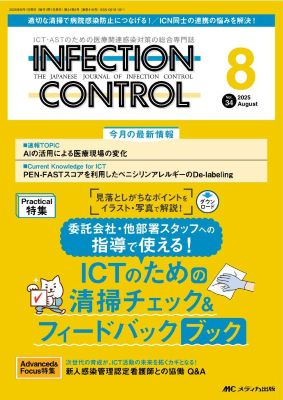
⇧最新情報は こちら から