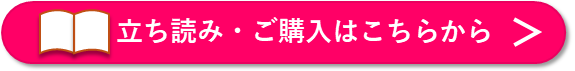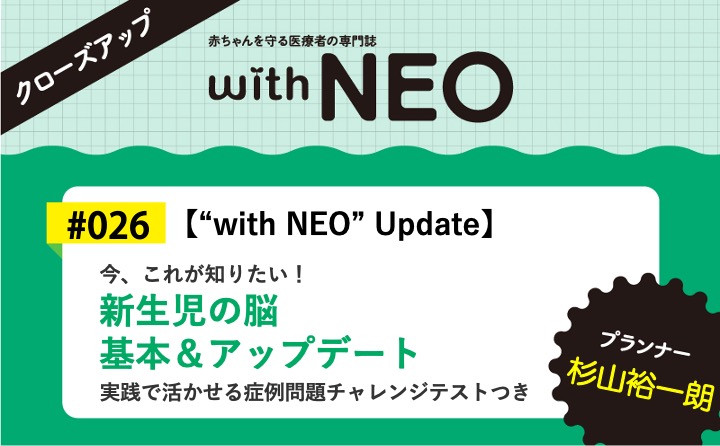研修医から若手医師、看護師の方にとって、新生児の脳のことを知っておくことはとても大事なことだと考えています。「脳」は、呼吸や循環などと比べて赤ちゃんの見た目からだけでは判断が難しいからです。例えば、SpO2のアラームがカンカンと鳴ると、「呼吸が苦しいのかな」と分かります。しかし、「白質(脳の部位)にダメージが入るな……。将来の認知機能は大丈夫かな……」というようなことは、NICUの中で働いているだけでは想像するのが難しいと思います。
例えば、早産で生まれた赤ちゃんにとってNICU内での管理が良かったかどうかは、「退院時に哺乳ができている」という点からだけでは判断できません。何年も先まで、そのお子さんを見ていく必要があります(歩けるか? 言葉を話すか? 普通学級へ行けるか? など)。
“退院した赤ちゃんがその後、どうなっていくのか”を新人・若手の時から理解していると、集中治療時期の赤ちゃんや家族への向き合い方が大きく変わってきます。普段の自身のケアや治療が赤ちゃんの将来にどれくらい影響するのか、赤ちゃんのこれからのために一緒に学びましょう♪
プランナー
日本赤十字社愛知医療センター
名古屋第一病院小児保健科副部長
杉山裕一朗
本記事は『with NEO』2025年4号特集扉からの再掲載です。
*** 今月号からスタート!! ***
新連載①
多職種の視点から見て・考える 赤ちゃんを支えるチーム医療の連携
<no.1>新生児科医師の視点から
本連載では、NICU・GCU入院前から退院後の生活に至るまで、赤ちゃんとその家族に関わりを持つ各職の視点から多職種の連携での情報共有の方法・タイミングやチーム医療の意義などを解説します。
新連載②
フィンランドから日本へ I’s Eyes 未来を見つめるファミリーセンタードケア
<第1回>これからの日本のファミリーセンタードケア
本連載では、実際のCCトレーニングを体験・実践した医師・看護師がどう感じ、CCトレーニン グが今後、施設をどう変える可能性があるかについて解説します。施設全体のFCCを変えることは容易ではありませんが、CCトレーニングが与える影響を例にとって、国内でどのようにFCCに取り組んでいけばよいかの一例を提示できればと期待しています。
新連載③
今、あらためて考える! 新生児科医師のためのフォローアップ NICU退院後から成人期までを流れで整理!
<第1回>新生児科医師がフォローアップを行うための基本的事項
2023年11月より設けられた「日本新生児成育医学会フォローアップ認定医」制度。本連載では、フォローアップを行う上で必要な知識・技能について、初めてフォローアップを行う医師が知っておくべきポイントを要点を絞って端的に解説します。