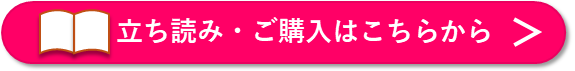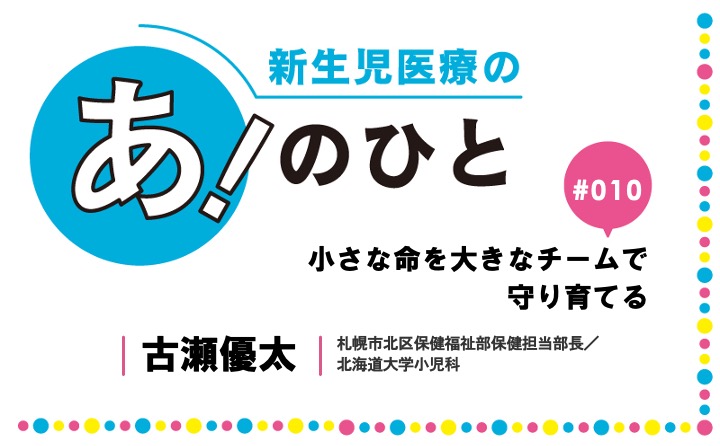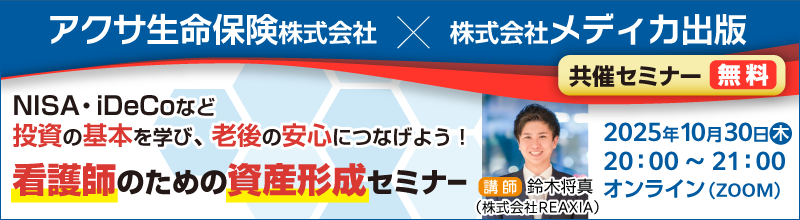小さな命を大きなチームで守り育てる
「子どもと楽しく遊びながら働きたい」と考えて2003年に北海道大学小児科に入局した私は、卒後1 年目の大学研修で初めてNICU に足を踏み入れました。耳に残るモニター音に毎晩うなされながらも、長和俊先生をはじめとする先輩医師に指導を受け、昼食をごちそうになる中で新生児医療に興味を持ちました。
卒後2年目の後半に北見赤十字病院のNICUに配属になりましたが、まもなくチーフの先生が体調不良で休職されたため、急遽赴任してくれた小児循環器の先生と二人でNICUの先頭で働くことになりました。必死に勉強しながら初めて担当した超低出生体重児は、言葉にできないほど愛おしく、抜管やコット移床の前日は楽しみと不安で眠れませんでした。そのような中、超優秀な臨床工学技士に教わりながら、メチルマロン酸血症の児を持続血液透析で救命できたことは大きな自信になりました。一方で、同じように透析を行った緊張性気胸後の腎不全の児は重症な脳出血を起こし、十分な準備ができないまま退院させた早産児が虐待を受け、医療的ケア児の家族から「こうなると分かっていて蘇生したんですか」と問い掛けられたこともありました。
楽しいことばかりではなく、手技に自信があるわけでも急性期のドタバタが好きなわけでもありませんでしたが、こういった子どもと家族を救えない自分たちが悔しくて、新生児医療の道に進むことを決めました。日本一のNICUで勉強したいと考え、2012年に神奈川県立こども医療センターに2年間留学させていただきました。さまざまな専門家との学会のような毎日から、チーム医療の偉大さを学び、県内の医療機関からの依頼で駆け付け、緊急処置後に三角搬送する経験からは、現場での対応力と周産期医療の現実を学びました。また、重症児をただ救命するだけではなく、データに基づき、児にとっての最善の方法を胎児期から家族と繰り返し話し合う姿勢から、新生児医療の責任を学びました。同じく国内留学に来ていた医師との家族ぐるみの交流は今も続いています。
2014年に北海道に戻り、今度は指導する側として、自分と同じ失敗をしない後輩を育てることに心血を注ぎました。今では当たり前に地方でも重症児を元気に退院させ、社会的ハイリスク家庭にも妊娠中からサポートを整える仕組みができ上がってきていると感じます。自分が担当した子どもと家族が幸せな人生を送れることをひたすら願い、そういう世の中を作っていきたいと考える日々です。
札幌市北区保健福祉部保健担当部長/北海道大学小児科
古瀬優太
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
す!がおのひとこと
2024年春に大学を離れることになり、以前から興味のあった行政医師になりました。医者生活20年を過ぎて新しい分野を一から勉強することになりますが、母子保健に関しては臨床医として限界までやってきた「その先」と向き合うことができています。周産期専門医やNCPRインストラクター資格を更新することが目下の課題ですが、子どもと家族が心豊かに暮らせる世の中をつくるチームの一員として働き続けています。
写真は、自分が最初に担当した超低出生体重児を、家族の許可をもらってカンガルーケアしている至福の一枚です。
本記事は『with NEO』2025年4号の連載「新生児医療の あ!のひと」からの再掲載です。