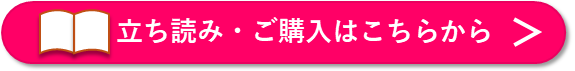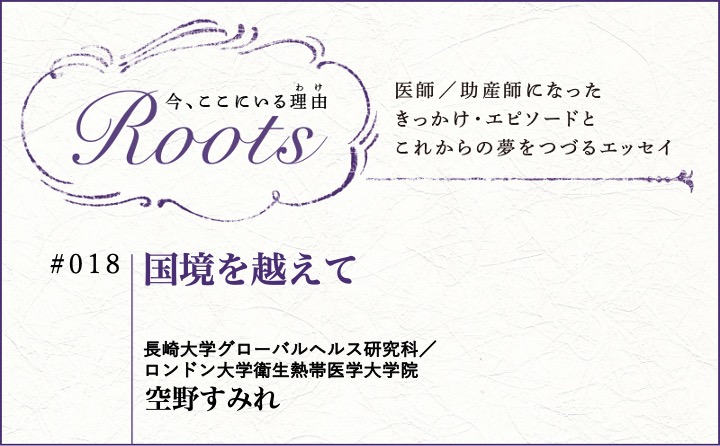空野すみれ
両親は学生運動の最後の世代だった。「平等な世の中を築きたかったが失敗した」と語る彼らは大学を中退し、工場で働く中で姉を授かった。やがて、母は資格を取って保育士として家計を担い、父は育児をしながら大学に復学した。当時は大阪北部に住んでおり、私は母が勤める保育園に通っていた。大阪市大正区にあるその園は、沖縄や外国にルーツをもつ子どもたちも多く通っていた。両親は外国人をよく家に招き、私は国を越えて彼らと遊び、アジア各国の料理に親しんだ。
自由な幼児期とは対照的に、小学校に入ってからは逆カルチャーショックを受けた。南部の“ごっつ大阪”な環境で育った私にとって、北部の上品な雰囲気と通じない大阪弁は衝撃だった。そして、空気が読めず、思ったことをすぐ口にしてしまう私は、しだいに浮いた存在になった。集団に合わせようと無理をした時期もあったが、疲れてしまい、単独行動の方が自分らしくいられると気づいたころ、少数ながら気の合う友人ができはじめた。
産婦人科専門医となり、国境なき医師団に入り、医療人道援助に関わった。日本では、妊産婦死亡を経験したことはなかったが、南スーダンやナイジェリアでは、子宮破裂や子癇、重症な子宮内感染が多く、女性が出産で亡くなるのを目の当たりにした。家父長制や一夫多妻制のもとで、女の子たちは教育を受けられず、幼いうちに結婚する。栄養失調やマラリアによる重症貧血に加え、未熟な骨盤で分娩がうまくいかず、産科フィスチュラを起こす例も多数経験した。いつ妊娠して子どもをもつか、という避妊に関する決定も夫が握る。これらの経験から、「国籍や経済的・社会的な背景に関係なく、女性が妊娠・出産で命を落とすことをなくしたい」「誰もが自分の人生を選択できる世界に貢献したい」と強く思うようになった。今は、学生として研究に取り組みながら、国際保健機関で母子保健の仕事を行っている。
母となった今、娘は私にあちこちに連れ回され、私が子どものころ以上に多国籍の人たちに囲まれて育っている。幼いころに出会った多様性と、その中に確かにあった温もりが、今の私の生き方や価値観を支える根っこになっている。特別なことではないけれど、私にとっては大切な軸になっている。
本記事は『ペリネイタルケア』2025年7月号の連載Rootsからの再掲載です。
➡︎連載「姿勢と呼吸をととのえるガスケアプローチ」の動画はこちらから