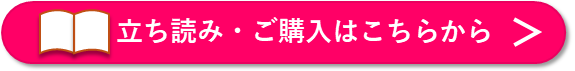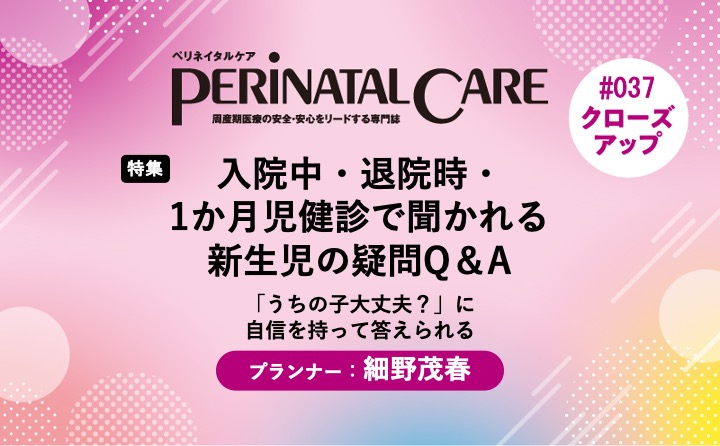母子保健法により、市町村において「1歳6か月児」および「3歳児」に対する乳幼児健康診査の実施が義務づけられている。また、乳児期(「3~6か月頃」および「9~11か月頃」)の健康診査についても、全国的に実施されている。2024(令和6)年度から新たに「1か月児」および「5歳児」に対する健康診査の費用の助成が始まった。1か月児健康診査は従来、分娩医療機関で行われており、1か月児健康診査までの児の対応は、産科医、助産師、看護師と保育士が中心となって担う施設も少なくない。そのため、産科入院中のご両親からの質問には、助産師・看護師が対応することがほとんどである。
出産後、親となり「お母さん・お父さん」として児のお世話が始まる。初めてのお子さんの場合は未知の体験であり、些細なことでも心配になる。今は「育児書」は死語で、情報源はインターネットやソーシャルメディアであり、ネットサーフィンの末にたどり着いた情報が正しいものであるかに悩んでしまう。AIの普及によって正しい情報にたどり着きやすくもなったが、相手の心理的状況を加味した温かみのある対応は、AIは医療者にはまだまだ及ばない。
本特集では、出生後から1か月児健康診査までに行われる検査や医療行為、または児の心配事について、頻度の高い項目をピックアップした。日頃から新生児管理および1か月児健診を行っている先生方に、ご両親に寄り添った説明を行うための知識について解説いただく。
プランナー
地域医療振興協会 練馬光が丘病院 小児科部長(新生児)/自治医科大学 客員教授
細野茂春
本記事は『ペリネイタルケア』2025年7月号特集扉からの再掲載です。
➡︎連載「姿勢と呼吸をととのえるガスケアプローチ」の動画はこちらから