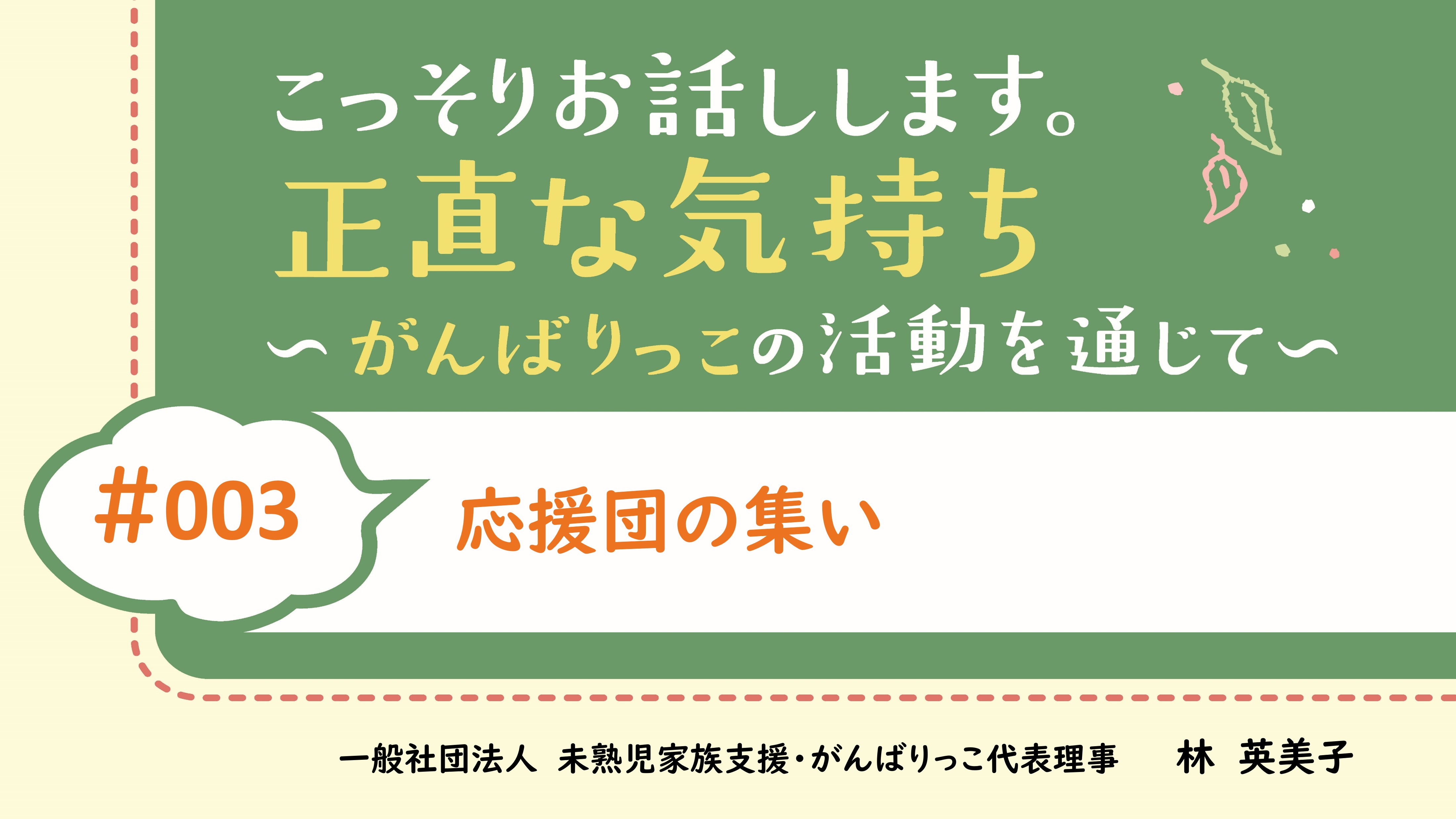はじめに
第1回では、がんばりっこ(未熟児・病児・障害児・お空っこ)の「集い」や「高尾山登山」について、第2回は全国7カ所で開催した「みんこど妖怪写真展」について紹介しました。今回は、がんばりっこを支える医療・福祉の専門職、“がんばりっこ応援団”の方々に向けた「応援団の集い」についてお伝えします。
開催のきっかけ
2022年の法人化に伴い、今後の活動について応援団登録者を対象にアンケートを実施しました。そのなかで、意外でもあり、同時に強く心を動かされたのが、「患者家族にとって大切にしていることを話せる場がほしい」「都道府県を越えた横のつながりがほしい」「現場の悩みや工夫を語り合いたい」といった声の多さでした。
がんばりっこの活動は、家族を対象とした場づくりが中心でしたが、これは応援団の皆さん自身が“支援する側”としての思いや葛藤を語れる場を求めていることの表れでもありました。
この声を受け、2022年9月より「応援団の集い」を開始しました。新生児科医、小児科医、NICU看護師、看護師長、PT(理学療法士)・OT(作業療法士)・ST(言語聴覚士)、心理士、保育士、臨床工学技士、社会福祉士、看護大学教員といった職種ごとの集いに加え、「退院後支援」「新人支援」「家族支援の悩み」など、テーマに基づいた集いも開催しました。オンラインでの開催ながら、率直であたたかな空気感のなか、職種を越えた対話の実現にもつながっています。これまでに開催された集いは14回にのぼります。
参加者からは、「他県や他職種の悩みを聞き、自分だけじゃないと気持ちが軽くなった」「がんばりっこ家族の視点を通じて、自分のケアを見直す機会になった」「新人の医療者が気軽に語れる場があることの重要性を感じた」「学生に子どもたちやご家族の頑張りをどう伝えるか考えさせられた」などの声が寄せられています。
話題は、現場の工夫から制度の課題、教育現場の悩みまで多岐にわたり、それぞれの立場でがんばる方々が、安心して“今の気持ち”を言葉にできる場となっています。
なかには、「今後は多職種での意見交換も深めたい」「全国の実践を持ち寄って、横断的なつながりを生みたい」といった声もあり、がんばりっこの活動が院内に留まらない、多職種連携のプラットフォームとしても期待されていることを実感します。応援団同士が顔を知り、声を交わすことで、学会や研究会などでの新たな協働へとつながっていく好循環も生まれています。
おわりに
がんばりっこでは、今後も家族の集いと並行して、応援団の集いを継続していく予定です。多職種の混合開催や、学会に合わせた対面での集いも視野に入れており、さらに横断的なつながりが生まれる場づくりを構想中です。
「支援する側」が、支援について悩み、迷い、語り合うことができる。それは専門職であるからこそ必要な営みではないでしょうか。お互いの経験や思いを共有し合うことが信頼につながり、結果として“がんばりっこ”たちへのより良い支援につながっていく。そんな循環を大切にしながら、これからも活動を続けていきます。
Take home message
“なんとか乗り切った感”で今日が終わったあなたへ。迷うのは、ちゃんと向き合ってる証拠です。同じように“がんばり中”な仲間が、全国にけっこういるんです。語って、笑って、ちょっとスッキリ。また明日、いけそうな気がしてきます。
※本記事の写真は許可を得て掲載しています。