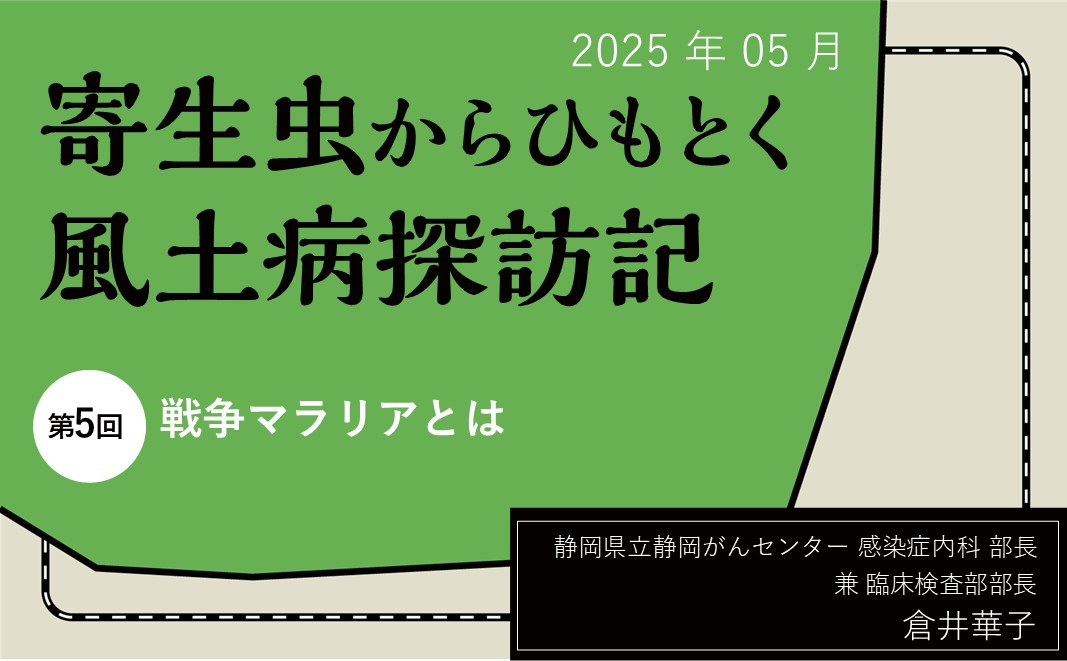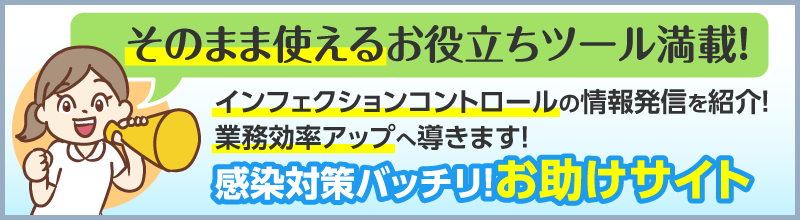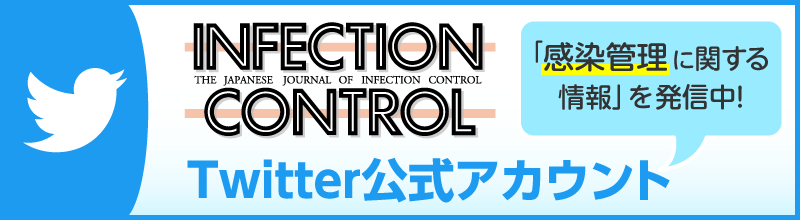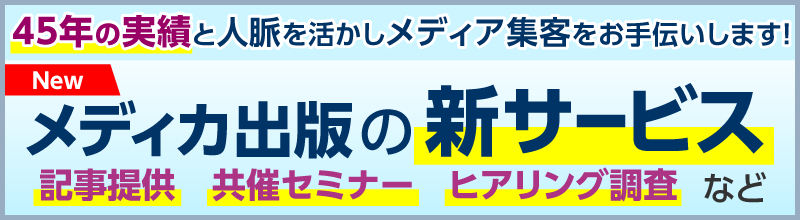第5回 戦争マラリアとは
*本連載は2019年1月号~12月号の本誌連載の再掲載記事になります。
*本記事の無断引用・転載を禁じます。
第4回ではハンセン病を取り上げたが、第5回も感染症の歴史を振り返る旅に出た。マラリアは蚊が媒介する原虫性感染症で、年間2億人以上が罹患する疾患である。国内では毎年40〜80例の輸入症例が発生しており、渡航者の疾患として認識されている。しかし日本にも土着のマラリアが存在していたことを知っているだろうか。
◎日本における土着マラリア
三日熱マラリア日本では、明治から昭和初期にかけて国内全土で三日熱マラリアが「土着マラリア」として流行していた。1916年(大正5年)の内務省衛生局報告によると、北海道全域のマラリア患者数は2,003人であったという。本州には琵琶湖周辺や愛知などに土着マラリアの記録が残っている。治療薬、生活環境の改善、湿地の土地改良や殺虫剤散布による媒介蚊の減少によって、土着マラリアは減少し続け、1959年の滋賀県彦根市の1例を最後に消滅した。
戦争マラリア沖縄では「戦争マラリア」と呼ばれる別の歴史がある。八重山地域では熱帯熱マラリアをコガタハマダラカが媒介しており、1737年には蔓延していたことが確認されている。「戦争マラリア」とは、第二次世界大戦時、沖縄県において疎開した一般住民がマラリアに罹患して多数が死亡したことを指す。
今回は石垣島にある八重山平和祈念館でお話を伺った。八重山平和祈念館は「戦争マラリア」を後世に正しく伝えるとともに、人間の尊厳が保障される社会の構築と恒久平和の実現を訴えるために設立された施設である。
沖縄県の八重山諸島では古くからマラリアの発生する地域があり、住民はその地域を避けて居住していた。しかし、第二次世界大戦の後期(1945年)一般住民の山岳地域への避難の命令が出され、住民はマラリアの流行地帯への移動を余儀なくされた。
住民は軍隊への編入や強制労働といった負荷に加え、農業や漁業も中断され、栄養不良から体力低下が進んでいった。こうしたなか、マラリア流行地に移動した多くの住民がマラリアに罹患し命を落としていった。波照間島では住民の99.8%が罹患し、3割が命を落とす悲惨な状況が発生している。住民に対する抗マラリア薬の支給はなく、マラリア患者は井戸水による冷却やヨモギなど民間療法に頼るしかなかった。マラリアにより一家全員が命を落とした家も多いという。八重山全体で約3,600人の命がマラリアによって奪われており、直接攻撃による死者よりもこの数は多い。
住民の定期的な採血検査と治療、DDT散布などの防蚊対策により、1961年を最後に患者の発生は確認されていない。
世界では多くの紛争が続いており、こうした地域では多くの命が感染症で失われている。感染症治療や感染症制御は平和のうえにしか成り立たないことを、八重山平和祈念館で痛感した。
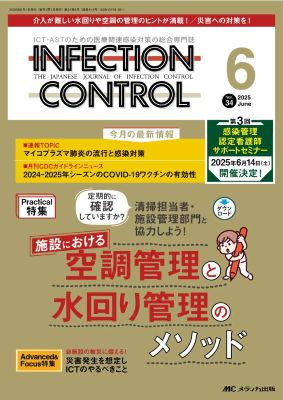
⇧最新情報は こちら から