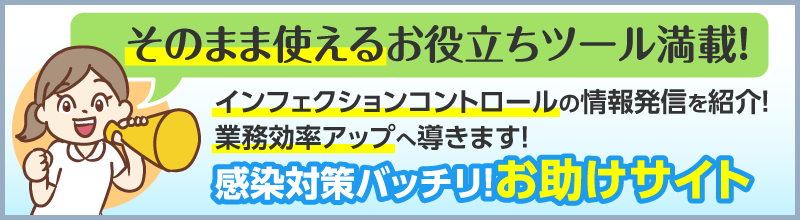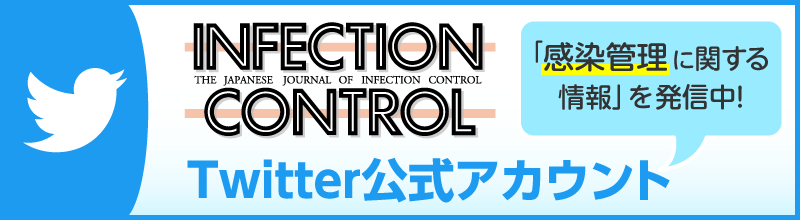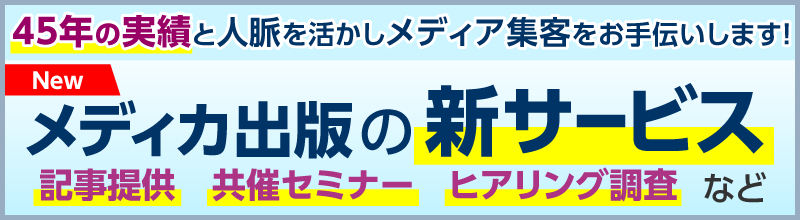矢野邦夫先生に「医療従事者における感染対策ガイドライン改訂版」についてご執筆いただきましたので、掲載いたします。
*INFECTION CONTROL34巻5月号の掲載の先行公開記事となります。
「医療従事者における感染対策ガイドライン改訂版」
CDCは「医療従事者における感染対策ガイドライン」を1998年に公開していたが、2024年にその一部を改訂した[https://www.cdc.gov/infection-control/media/pdfs/Guideline-IC-HCP-H.pdf]。2つのガイドラインの相違点を解説する。
相違点
1998年のガイドラインは、医療従事者の感染管理に関する包括的なガイダンスを提供しており、さまざまな感染症に対する推奨事項が含まれていた。2024年のガイドラインは、特定の感染症(サイトメガロウイルス、ジフテリア、A群レンサ球菌など)に焦点を当て、医療従事者への感染伝播のリスクを管理するための推奨事項を更新している。特に、曝露後の対応、就業制限、検査方法について明確にしている。
サイトメガロウイルス(CMV)
1998年のガイドラインでは、妊娠中の医療従事者に対し、CMV感染のリスクについてカウンセリングを行うこと、および感染の可能性がある患者のケアから妊娠中の医療従事者を日常的に除外しないことを推奨していた。ただし、「必要に応じて職場での業務調整を検討する」という推奨が含まれていた。2024年のガイドラインでは、CMVに曝露した、または活動性CMV感染症のある医療従事者に対し、労働制限は必要ないと明確に述べており、この推奨は、妊娠中の医療従事者にも適用される。すなわち、妊娠中の医療従事者も、ほかの医療従事者と同様に、標準予防策を遵守することで、安全に業務を継続できるとされた。
ジフテリア
1998年のガイドラインでは、ジフテリアに曝露した医療従事者に対して、曝露後のフォローアップと就業制限について言及されていたが、詳細な手順は不明確であった。2024年のガイドラインでは、曝露後の予防措置として、ワクチン接種と抗菌薬の投与を推奨している。具体的には、曝露後予防としてジフテリアトキソイドを含むワクチンの接種と、ベンジルペニシリンベンザチンの筋肉注射、または経口エリスロマイシンの7~10日間の投与を推奨している。
A群レンサ球菌
1998年のガイドラインでは、A群レンサ球菌感染症に対する医療従事者の取り扱いについて、具体的な推奨事項は少なく、感染した医療従事者の就業制限について言及していた。2024年のガイドラインでは、A群レンサ球菌に曝露した医療従事者に対する予防措置や就業制限は不要であると明記されている。ただし、感染が疑われる場合は、検査を行い、効果的な抗菌薬治療の開始後24時間、および皮膚病変が適切に覆われている場合に職場復帰が可能とした。
風疹
1998年のガイドラインでは、風疹免疫のない医療従事者へのワクチン接種と曝露後の管理に関する一般的な推奨事項が含まれている。2024年のガイドラインでは、風疹に曝露した免疫のある医療従事者には就業制限は不要であるが、曝露後7~23日間は症状をモニタリングする必要があるとされた。免疫がない医療従事者は、曝露後7~23日間は就業制限される。
百日咳
1998年のガイドラインでは、百日咳の疑いのある患者に濃厚接触した医療従事者には予防抗菌薬を推奨しており、全細胞性百日咳ワクチンは医療従事者には接種しないとされていた。2024年のガイドラインでは、曝露した無症状の医療従事者に対しては予防抗菌薬(アジスロマイシンやエリスロマイシン)を推奨している。予防抗菌薬の投与を受けない場合は、感染リスクの高い人と接触しないように就業制限を設けることを勧めている。百日咳の曝露後予防としては抗菌薬投与が推奨されるが、ワクチン接種は曝露後の緊急的な対応ではなく、日ごろからの感染対策の一環として推奨されている。
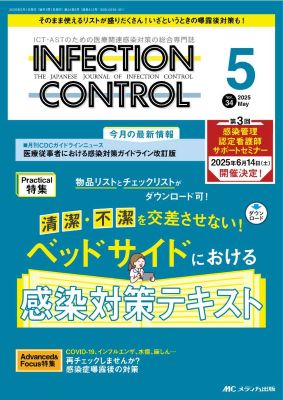
(本誌のご購入はこちらから)
*INFECTION CONTROL34巻5月号の掲載の先行公開記事となります。
*本記事の無断引用・転載を禁じます。