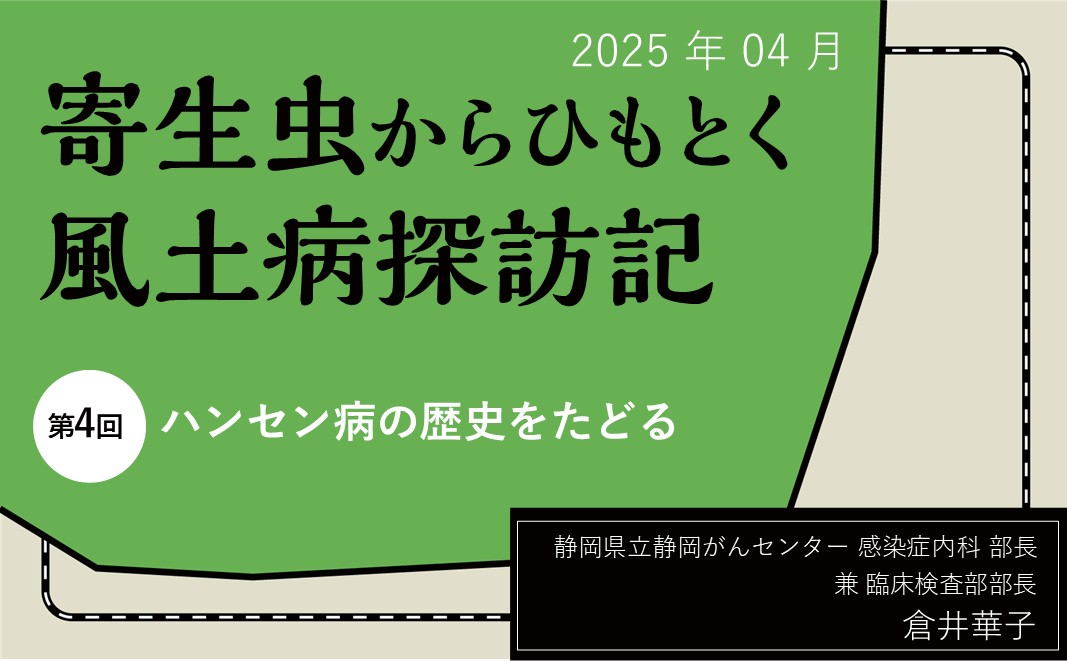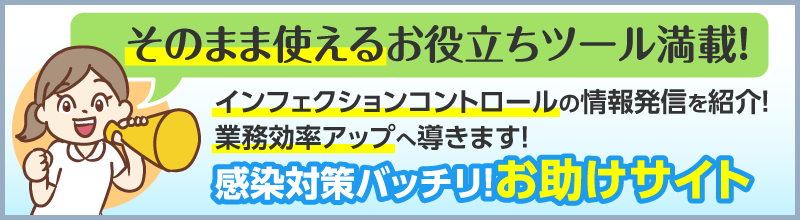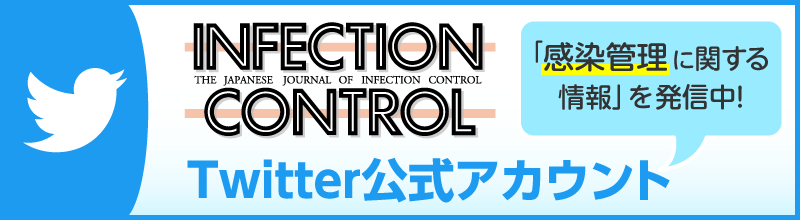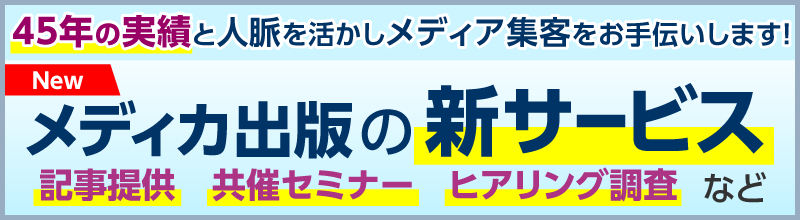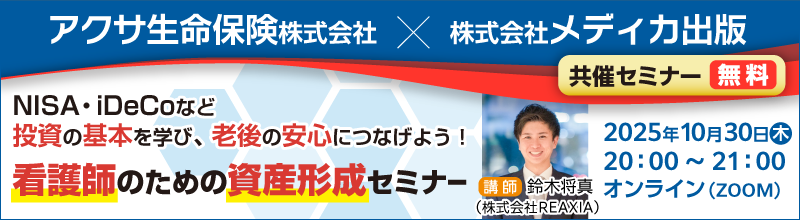第4回 ハンセン病の歴史をたどる
*本連載は2019年1月号~12月号の本誌連載の再掲載記事になります。
*本記事の無断引用・転載を禁じます。
今回は、寄生虫疾患から外れるが、感染対策の歴史で重要なハンセン病をテーマにしたい。
ハンセン病はかつて「らい」と呼ばれていたが、「らい予防法の廃止に関する法律」に伴い、1996年(平成8年)病原菌を発見したノルウェーの細菌学者アルマウェル・ハンセンの名前をとってハンセン病と改称された。私たちはどれくらいハンセン病について知っているだろうか?
感染症は正しい啓発活動を行わなければ差別や偏見を生み出す。感染症に携わるものとして、ハンセン病の歴史と問題点を学びたく、今回のコラムに取り上げた。
◎ハンセン病について
ハンセン病の原因はらい菌であり、抗酸菌の一種である。末梢神経障害や皮膚症状を起こす例が多く、進行すれば四肢や顔面の変形や潰瘍形成、眼症状などがみられる。感染性は低いが見た目で診断しやすいことから、古くから差別の対象となっている疾患である。アフリカや東南アジアに行くと今でも多くの患者を目にする(図1)。
 図1 四肢変形と難治性腫瘍で入院するハンセン病の患者
図1 四肢変形と難治性腫瘍で入院するハンセン病の患者
◎神山復生病院を訪れて
静岡には、日本初のハンセン病治療および療養施設である神山復生病院がある。定期的にハンセン病の勉強会を開催しており、今回は江藤秀顕先生にお話を伺い記念館を見せていただいた。神山復生病院は1889年(明治22年)パリ外国宣教会のジェルマン・レジェ・テストヴィド神父が開設した私立の療養施設である。キリスト教の信念に基づき、ほかのハンセン病施設に比べ、地域住民との交流や外出なども許されており制限が少ない施設であったようである。今では入所者が高齢化し、自力での活動が困難となり、歴史を語る人も減ってきた。
ハンセン病は古くから穢れの対象として差別され、1907年成立の法律「らい予防に関する件」により患者の療養所への隔離が始まった。患者は生まれ育った土地や家族から切り離され、外出の禁止や生涯隔離が定められた。1940年代に治療薬であるプロミンが投与され、治癒する疾患となった後も隔離の方針は1996年まで続いた。専門家は隔離対策こそが正しいとが信じ、不要な隔離対策が行われていた歴史がある。
過去の話として片づけてよいのだろうか?エボラ出血熱や重症急性呼吸器症候群(SARS)など国民に馴染みのない感染症は未だ恐怖の対象となっている。また、耐性菌による隔離は必要な対策として私たちは行っているが、患者のQOLを損ねる一面も持つ。感染対策の専門家の意見が、ときに患者を傷つける武器となることを私たちは忘れてはならない。
ハンセン病の歴史や患者の手記など、今回の記事をきっかけに数冊の本を読んだが、私の中でまだ消化しきれていない。今後も勉強会に参加し続けようと思う。全国にはほかにもハンセン病の記念館や資料館が存在する。日本のハンセン病政策が抱えていた問題、隔離されていた人の思いや日常、こうしたものを教えてくれるかけがえのない場所をぜひ一度訪れてほしい。神山復生病院では残り少なくなったハンセン病入所者全員に心を配り、最後まで支えようというスタッフの思いが伝わってきた。今は穏やかな時間が流れていた。
■文 献
1) 国立ハンセン病資料館.関連リンク.http://www.hansen-dis.jp/00oth/link
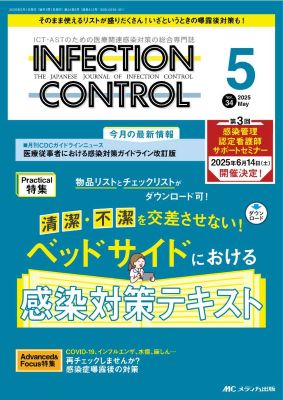
⇧最新情報は こちら から