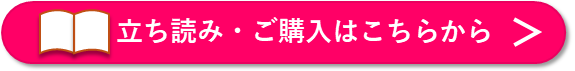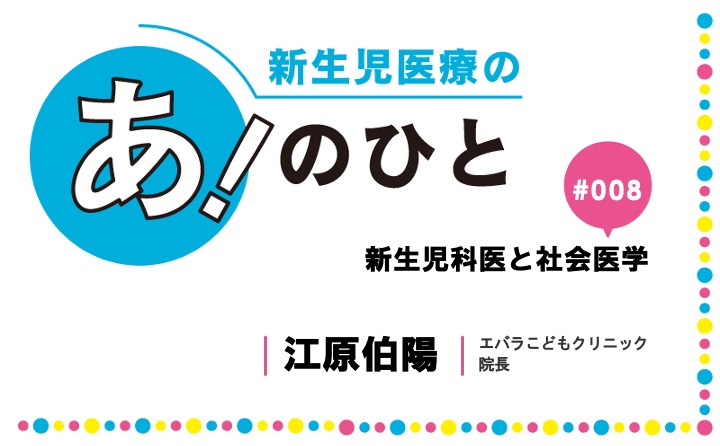新生児科医と社会医学
医学部に入ってしばらく経ったころ、学校に行けない障害児を支えるワークキャンプに参加した。というのも、当時、障害者施設の医師不足で、大阪大学で母子保健を教えていた叔父・張 知夫が引っ張り出されて勤務していたことが影響していたからだと思う。そういう経緯で、生まれてくる病的新生児を早期に治療すれば、その子はそれ以降、健やかに育つだろうとの思いから、卒後は神奈川県立こども医療センターで小児科研修後に新生児科を選んだ。
大阪に母子総合医療センターができるというので、その前に海外を見ておこうとシカゴ大学の新生児科でしばらくお世話になった。当時、大学があるシカゴの南部は黒人居住区で、貧困や麻薬中毒、妊婦の6割が未成年など、ハイリスク新生児を研究する人にとってはまさに宝庫であった。張らによる海外での社会調査により、乳児死亡率が高かった大阪府の南部に母子センターを設立したインパクトは強く、数年のうちに乳児死亡率が北部並みにまで改善した。また後に米国国立衛生研究所(NIH)の共同研究員として、死亡率を多方面から国際比較する機会を得、日本の特徴として新生児の出生体重のばらつきが非常に少なく、妊婦の健康管理が行き渡っていることを知った。
しかし、後遺症を抱えたままNICU から退院していった子どもたちの生活はどうなのだろう? と気になり、思い切ってこどもクリニックを開業し、地域で彼らに接することができるようにした。当時、脳性麻痺、先天異常、重度の分娩障害などの子どもたちを診てくれる小児科医は少なく、それで全国に散らばる元新生児科医らに呼び掛けて「赤ちゃん成育ネットワーク」を立ち上げた。医療的ケア児に必要な気管カニューレや胃瘻交換、在宅人工呼吸器の操作などを皆で学んだ。
しかし、これら在宅で医療的ケアが必要な子どもを世話する家族(特に母親)の睡眠時間はわずか5時間しかなく、しかも断続的に児の喀痰吸引や体位変換をしなければならず、さらに日中は他の兄弟の世話や家事に追われる極限の状況にある。なのに、憲法で保障されるはずの基本的人権は福祉報酬の低さのために、利用できる福祉事務所が極めて少ないのが実情である。そういう意味で、新生児医学は何もNICU 内だけの出来事だけでなく、退院後に障害を抱えて苦悩するファミリーも含めて、児の長い一生にまで影響し得る社会医学的な側面を持つ医療であると意識するようになった。
自分の半生を振り返ると、シカゴ大学で上司のProf. Kwang Sun Lee から周産期疫学を学び、また大阪母子医療センターでは竹内 徹先生から母と子のきずな、さらに退職後も藤村正哲先生よりハイリスク児のフォローアップ解析や医療提供体制の在り方について学べたのは、まさにラッキーだったとしか言いようがない。
エバラこどもクリニック院長
江原伯陽
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
す!がおのひとこと
小さい時、いつもショパンのノクターンを弾く母の足もとでまとわりついていたせいか、知らず知らずのうちに、音楽は僕の魂を慰める必要不可欠の伴侶になっていた。淋しい時、落ち込んだ時、自らを奮い立たせたい時、その時に応じて聞きたい曲と散歩コースはいつも決まっている。
先日、高校時代の恩師を追悼するコンサートが開催され、数十年ぶりにコーラス部の仲間と歌ったアヴェ・マリアは、やはり胸を捉えて放さない余韻として残った。いつかはヨーロッパの教会を巡りながら、宗教音楽に浸る旅に出たいと願っている。
本記事は『with NEO』2025年2号の連載「新生児医療の あ!のひと」からの再掲載です。