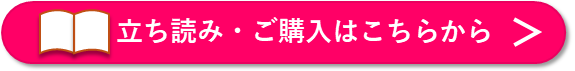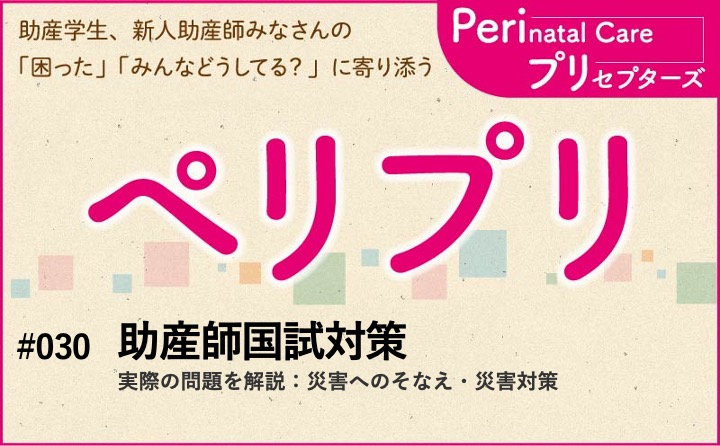こんにちは! 助産師のキャリーです。今年も残すところわずかとなり、冬の寒さが一層厳しく感じられる季節となりました。さて、今月のテーマは「国試対策」です。助産師国家試験を控えた皆さん、試験勉強を本格的に進めている時期かと思いますが、どうか無理せず、自分のペースで学び続けてください。
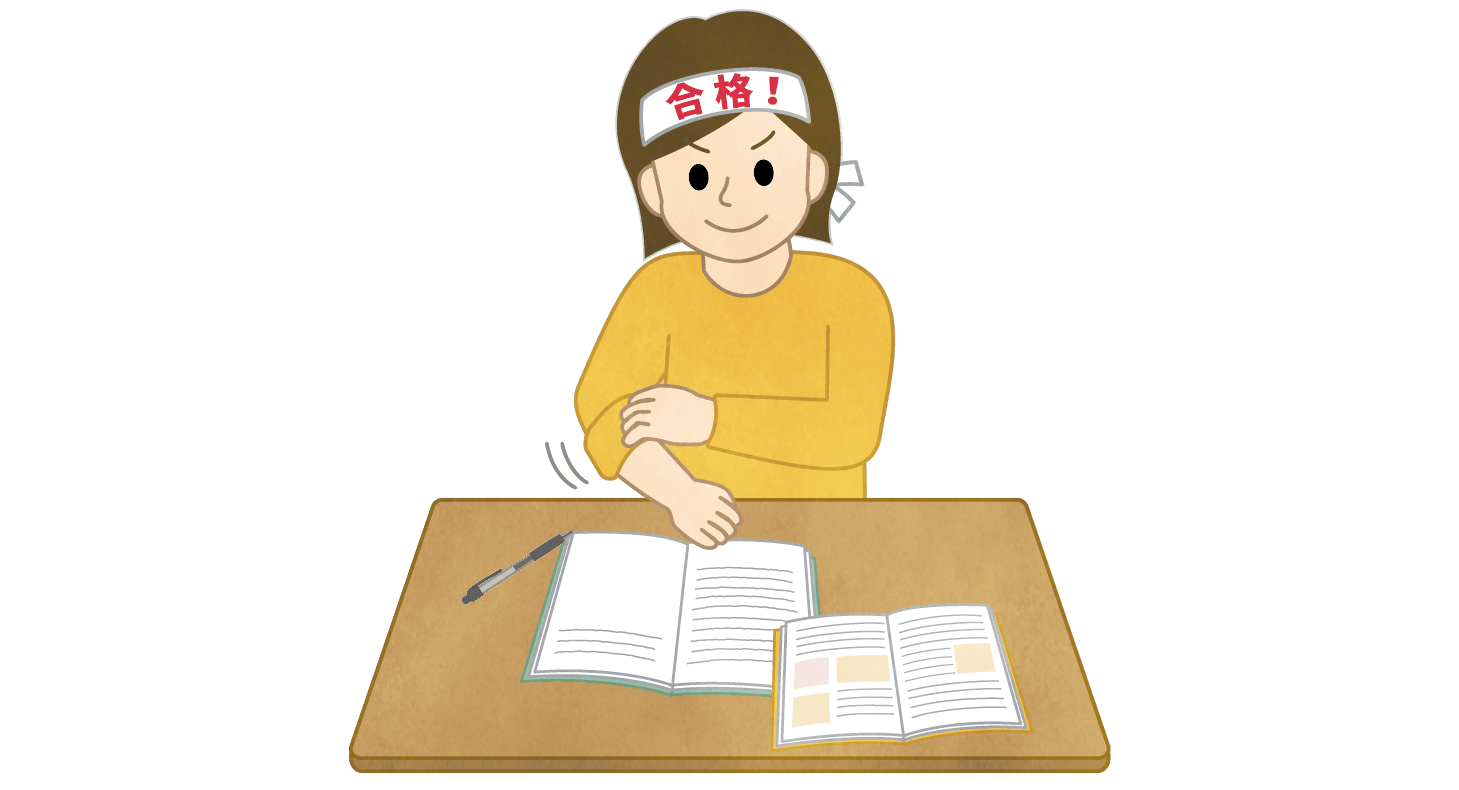
【災害時の助産師の役割や対応について考える】
今回は、能登半島地震をきっかけに、災害時における助産師の役割や対応について一緒に考えられたらと思います。また、被災された方々にはお見舞いと能登の復興を心より願っています。
過去3年間の災害関連の出題(第105回:午前問題23、第106回:午後問題48~50、第107回:午前問題40)を実際に解きながら、『助産管理』の教科書や日本看護協会の「改訂版 分娩取扱施設における災害発生時の対応マニュアル作成ガイド」を私も読み返してみました。
そこから、実際の国家試験で正答していくためには、以下の3つの知識がポイントとなると思うのでまとめてみました。一緒に確認していきましょう!!
1.初期対応
災害時における産科病棟の初期対応で重要なのは妊産褥婦と新生児の安否確認、次いで医療機器などの作動確認です。 アクションカード(緊急時にスタッフに配布される、個々の役割と何をすべきかを 具体的に記載したカード)を基に被災状況の確認を行います。
停電などの影響を考慮し、母子の安全確保のために非常用電源の確認が重要です。また、スタッフ自身の安全も大切ですね。病棟運営の維持には人員調整が不可欠です。
被災直後に身体的不調の訴えはなくても、被災により食事・運動・水分が不足しているため、妊産婦と新生児の状態が変化するかもしれません。そのため、母体搬送が可能な周産期医療施設の情報を収集する必要性も出てきます。
受け入れ病院では、周産期トリアージブースの設置を考えた人員配置、医師との役割分担も重要になってきます。
2.災害への備え
災害は非日常的ではありますが、それ故に災害訓練や避難経路の確認は大切です。いざというときに動けるように、マニュアルの見直しも大切です。自施設の耐震性、防火性は? 防火器具の場所と使い方は? 避難誘導方法は? など、日頃より確認が必要です。非常持ち出し袋の点検も日常的に行う習慣があるといいですね。
3.避難経路と方法
避難の具体的な方法を問う問題も出題されています。「改訂版 分娩取扱施設における災害発生時の対応マニュアル作成ガイド」の46ページに詳細があるので、一読されることをおススメします。要点は以下の3点です。
●母児同室中の新生児は母親と一緒に避難してもらいます。新生児が病児室にいる場合は、母親と新生児のネームバンドを照合してから預け、避難してもらいます。母親が退院している患児は、保温ブランケットで覆って抱っこもしくは新生児避難具に収容し避難します。
●歩行可能な妊産婦は階段や避難用スロープを使用して避難し、エレベーターの使用は避けます。
●意識レベルが低下している患者や術直後の患者はトリアージに基づいて担送され、赤いマークで重症患者を識別し、優先的に避難させます。
上記はほんの一部分の要点ですが、少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。災害時の対応に関する知識は、試験対策だけでなく、将来の現場で実際に役立つ大切な力となります。最後に、国家試験合格を心より応援しています。皆さんの努力が報われますように。
* * *
もっと深く勉強したいというあなた! メディカ出版の『実践! 小児・周産期医療現場の災害対策テキスト』もおススメです♡
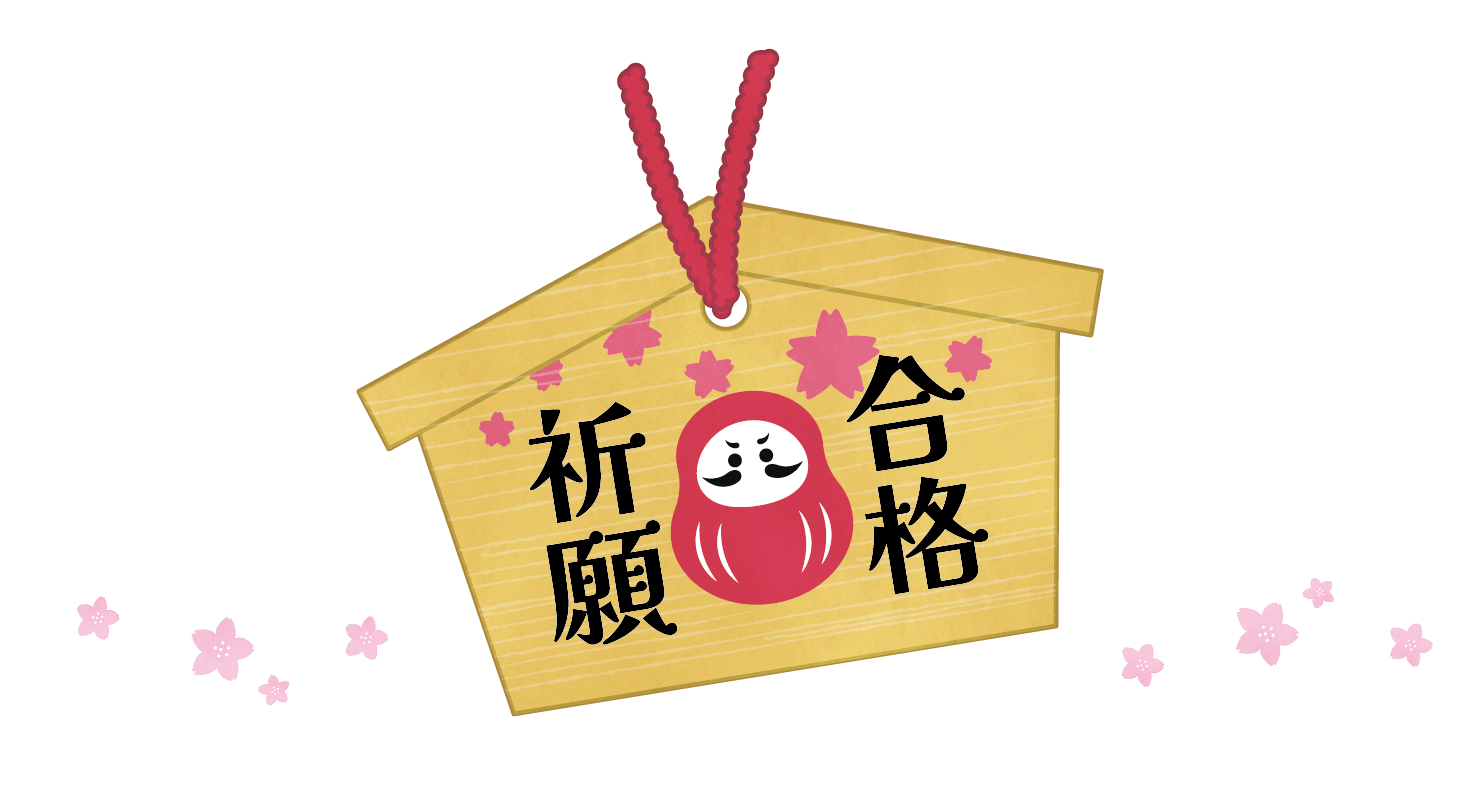
❤ペリプリ(Perinatal Care プリセプターズ)メンバー
助産師キャリー/アドバンス助産師
X(Twitter) Instagram
受験者必携の助産師国家試験過去問題集
第107回助産師国家試験問題を含む過去5回・全550問を完全収載!
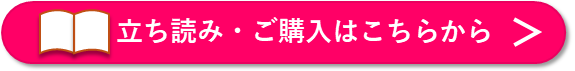
スキマ時間で要点が身に付く問題集
過去問題集と併せて学習して、実力アップ!