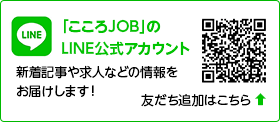多くの心理士が活躍する精神科領域。精神科医で、認知行動療法の第一人者として知られる、一般社団法人認知行動療法研修開発センター理事長・ストレスマネジメントネットワーク代表の大野 裕先生に、公認心理師への期待について伺った。
― 先生は、日頃、心理士といろいろな場面で協働されている中で、心理士に対してどのようなことを感じていらっしゃいますか。
大野 医療、職域(産業)、福祉など、活躍していただく場面は多いと感じています。ただ、非常に優秀な方と、まだ慣れておられない方がいて、そのバラツキが気になりますね。公認心理師について言えば、どのような活躍を期待できるかについてはまだこれから、というところでしょうか。心理士だけでなく、いろいろな経歴の方が資格を取っているので、今後、どのようにスキルアップしていくかが、非常に重要になってくると思います。
― スキルアップを図るにも、心理士は患者や相談者と接しながら経験を積み、学んでいかなくてはならないところに難しさを感じます。
大野 その難しさは、実は医師も同じです。経験の浅い心理士や医師が患者やユーザー(相談者)と安心して接することができる環境づくりが必要ですね。心理士自身のスキルアップが図れると同時に、患者やユーザーに役立つように貢献できる仕組みを、同時に考えていくことが大切です。
医師の教育では、いろいろな患者の治療をしながら上司に報告をして指導を受ける、一緒に診察を行う、先輩の診察に陪席する、などの方法があります。心理士も研修会など、座学で学ぶことも必要ですが、面接を適切に行えるようにきちんとモニターしたり、スーパービジョンの仕組みをつくったりすることは重要だと思います。
― どのような心理士であれば、医師は安心して協働できるでしょうか。
大野 求められている能力を身につけた上で、ただ指示を受けて動くのではなく、自分の意見をしっかり持っている方がいいですね。
医療の場面では、最終的な責任をとるのは医師です。そのため、医師には全体を見渡して状況をコントロールしなくてはいけないという思いがあります。その思いを受け止める立場にある心理士には、医師に意見を言いにくいと感じる人もいると思います。
医療的なことは医師から患者に伝える必要がありますが、医師がすべてを担うことはできません。時間の制約があり、なかなかゆっくり患者の話を聞けない自分に代わって、心理的なサポートを心理士に頼みたい。そう考えている医師は多いと思います。医師は忙しくゆっくり話を聞く時間がないことも多いので、それができる心理士と協働できるのは大きなメリットです。
患者側も同様に、心理士に話を聞いてほしいというニーズは高いと思います。医師と心理士の連携がスムーズにいかないのでは、そのニーズにうまく応えられません。きちんと意見を交わした上で、互いに協働できる部分を見つけていけるとよいのではないでしょうか。
― どのようにして協働していけばよいでしょうか。
大野 例えば、私がアメリカにいたとき、医師は、患者の診察と同じくらい重要な仕事として、他職種とのミーティングの時間をもっていました。心理士とのミーティング、看護師とのミーティング、多職種合同のミーティングなどのほか、患者も参加するミーティングや、家族も参加するミーティングも行っていました。そういう環境の中で、多職種が互いに持っているものを出し合える体制をつくり、患者を支えていくことが必要だと思います。残念ながら、まだ日本ではあまり行われていないのですが……。
― 日本ではなぜ行われていないのでしょうか。
大野 日本は、物質科学的な考え方が主流なのですね。例えば、病気の原因を、体のある器官が悪いからだと考える。ところが実際、病気には、その人が生活している環境や人間関係がかなり影響しています。精神疾患の場合は、特にそういうことが多いのですが、そこが抜け落ちていることがあるのです。
精神的な問題の場合、困っている方、ユーザーに何が提供できるのかという視点での仕組みづくりが必要です。つまり、医療が一方的に何かを提供するのではなく、その方の”生きづらさ“を軽減し、生活しやすくための仕組みづくりをしていくことです。今後、そこで、心理士の果たす役割は非常に大きくなっていくと思いますね。
― 日本では、“生きづらさ“のような目に見えないものを評価し、対応していくことへの関心があまり高くないように感じます。
大野 そうですね。そういう意味では、認知症のような国民全体で考える必要がある課題への取り組みから、変わっていく可能性があるのではないでしょうか。認知症は病気としてではなく、加齢が早く進んだ状態ととらえて支援したほうが良いと指摘している医師もいます。つまり、誰もが認知症のような状態になる可能性がある。だから、国民全体としてどう支えていくかという視点が重要だということです。
精神医療の領域では、診断はその人を理解する上での一つの手がかりでしかありません。うつ病や認知症、発達障害といっても、人それぞれのうつ病があり、認知症があり、発達障害があるわけです。ですから、例えば胃がんのように病変を切り取れば良くなる、というものではありません。その人の置かれている環境の中で、その人がどのように生きていくのかを共に考えていくことが非常に重要になってきます。
そうなると、病気を治療して治癒や回復を目指す「医療モデル」だけでは、当然、不十分です。疾患だけを見るのではなく、“人間”を見ていくことが大切なのです。今後は、そうした場面でも、今まで以上に心理社会的関わりを考えていく必要が出てくるだろうと思います。
― 心理社会的関わりの重要性を広く理解してもらうにはどうすればよいでしょうか。
大野 私は長く認知行動療法に取り組んでいますが、薬だけでは治療効果が上がらなかった方に対して認知行動療法を適用すると効果が高くなることを、データを示し、エビデンスを出してきました。心理士も、心理的アプローチが患者やユーザーにとって役に立つことを示すには、エビデンスを出していくことが求められます。そして、繰り返しになりますが、同時に心理士としてスキルアップを図ることも必要です。これからさらにエビデンスを出していくためにも、カウンセリングスキルなどをいっそう磨いていってほしいと思います。
*認知行動療法の第一人者である大野 裕先生が、認知行動療法と、認知行動療法における心理士の役割などについて語った記事はこちら
(インタビュー・文:介護福祉ライター/公認心理師・臨床心理士・社会福祉士 宮下公美子)
― 先生は、日頃、心理士といろいろな場面で協働されている中で、心理士に対してどのようなことを感じていらっしゃいますか。
大野 医療、職域(産業)、福祉など、活躍していただく場面は多いと感じています。ただ、非常に優秀な方と、まだ慣れておられない方がいて、そのバラツキが気になりますね。公認心理師について言えば、どのような活躍を期待できるかについてはまだこれから、というところでしょうか。心理士だけでなく、いろいろな経歴の方が資格を取っているので、今後、どのようにスキルアップしていくかが、非常に重要になってくると思います。
― スキルアップを図るにも、心理士は患者や相談者と接しながら経験を積み、学んでいかなくてはならないところに難しさを感じます。
大野 その難しさは、実は医師も同じです。経験の浅い心理士や医師が患者やユーザー(相談者)と安心して接することができる環境づくりが必要ですね。心理士自身のスキルアップが図れると同時に、患者やユーザーに役立つように貢献できる仕組みを、同時に考えていくことが大切です。
医師の教育では、いろいろな患者の治療をしながら上司に報告をして指導を受ける、一緒に診察を行う、先輩の診察に陪席する、などの方法があります。心理士も研修会など、座学で学ぶことも必要ですが、面接を適切に行えるようにきちんとモニターしたり、スーパービジョンの仕組みをつくったりすることは重要だと思います。
― どのような心理士であれば、医師は安心して協働できるでしょうか。
大野 求められている能力を身につけた上で、ただ指示を受けて動くのではなく、自分の意見をしっかり持っている方がいいですね。
医療の場面では、最終的な責任をとるのは医師です。そのため、医師には全体を見渡して状況をコントロールしなくてはいけないという思いがあります。その思いを受け止める立場にある心理士には、医師に意見を言いにくいと感じる人もいると思います。
医療的なことは医師から患者に伝える必要がありますが、医師がすべてを担うことはできません。時間の制約があり、なかなかゆっくり患者の話を聞けない自分に代わって、心理的なサポートを心理士に頼みたい。そう考えている医師は多いと思います。医師は忙しくゆっくり話を聞く時間がないことも多いので、それができる心理士と協働できるのは大きなメリットです。
患者側も同様に、心理士に話を聞いてほしいというニーズは高いと思います。医師と心理士の連携がスムーズにいかないのでは、そのニーズにうまく応えられません。きちんと意見を交わした上で、互いに協働できる部分を見つけていけるとよいのではないでしょうか。
― どのようにして協働していけばよいでしょうか。
大野 例えば、私がアメリカにいたとき、医師は、患者の診察と同じくらい重要な仕事として、他職種とのミーティングの時間をもっていました。心理士とのミーティング、看護師とのミーティング、多職種合同のミーティングなどのほか、患者も参加するミーティングや、家族も参加するミーティングも行っていました。そういう環境の中で、多職種が互いに持っているものを出し合える体制をつくり、患者を支えていくことが必要だと思います。残念ながら、まだ日本ではあまり行われていないのですが……。
― 日本ではなぜ行われていないのでしょうか。
大野 日本は、物質科学的な考え方が主流なのですね。例えば、病気の原因を、体のある器官が悪いからだと考える。ところが実際、病気には、その人が生活している環境や人間関係がかなり影響しています。精神疾患の場合は、特にそういうことが多いのですが、そこが抜け落ちていることがあるのです。
精神的な問題の場合、困っている方、ユーザーに何が提供できるのかという視点での仕組みづくりが必要です。つまり、医療が一方的に何かを提供するのではなく、その方の”生きづらさ“を軽減し、生活しやすくための仕組みづくりをしていくことです。今後、そこで、心理士の果たす役割は非常に大きくなっていくと思いますね。
― 日本では、“生きづらさ“のような目に見えないものを評価し、対応していくことへの関心があまり高くないように感じます。
大野 そうですね。そういう意味では、認知症のような国民全体で考える必要がある課題への取り組みから、変わっていく可能性があるのではないでしょうか。認知症は病気としてではなく、加齢が早く進んだ状態ととらえて支援したほうが良いと指摘している医師もいます。つまり、誰もが認知症のような状態になる可能性がある。だから、国民全体としてどう支えていくかという視点が重要だということです。
精神医療の領域では、診断はその人を理解する上での一つの手がかりでしかありません。うつ病や認知症、発達障害といっても、人それぞれのうつ病があり、認知症があり、発達障害があるわけです。ですから、例えば胃がんのように病変を切り取れば良くなる、というものではありません。その人の置かれている環境の中で、その人がどのように生きていくのかを共に考えていくことが非常に重要になってきます。
そうなると、病気を治療して治癒や回復を目指す「医療モデル」だけでは、当然、不十分です。疾患だけを見るのではなく、“人間”を見ていくことが大切なのです。今後は、そうした場面でも、今まで以上に心理社会的関わりを考えていく必要が出てくるだろうと思います。
― 心理社会的関わりの重要性を広く理解してもらうにはどうすればよいでしょうか。
大野 私は長く認知行動療法に取り組んでいますが、薬だけでは治療効果が上がらなかった方に対して認知行動療法を適用すると効果が高くなることを、データを示し、エビデンスを出してきました。心理士も、心理的アプローチが患者やユーザーにとって役に立つことを示すには、エビデンスを出していくことが求められます。そして、繰り返しになりますが、同時に心理士としてスキルアップを図ることも必要です。これからさらにエビデンスを出していくためにも、カウンセリングスキルなどをいっそう磨いていってほしいと思います。
*認知行動療法の第一人者である大野 裕先生が、認知行動療法と、認知行動療法における心理士の役割などについて語った記事はこちら
(インタビュー・文:介護福祉ライター/公認心理師・臨床心理士・社会福祉士 宮下公美子)