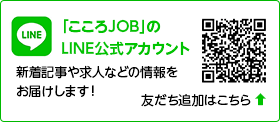新型コロナウイルスの感染拡大による自宅療養者の増加などもあり、注目が高まっている在宅医療。在宅医療を行う医療法人社団悠翔会 理事長・診療部長の佐々木 淳先生のインタビューを2回に分けて紹介している。前編では在宅での「看取り」までの自己受容の過程で心理士が求められているという話があった。今回は、認知症のある人へのケア、そして、在宅で心理士に求められているものについて伺った。
― 前回挙げてくださった「看取り」のほかに、在宅では、認知症がある人にも心理的サポートが求められているとのことですが、心理士にどのような役割を期待されていますか。
佐々木 「認知症」という呼称は誰もが知るようになりましたが、「認知症」についての正しい知識と理解はまだまだ広がっていません。特に、本人やご家族が偏見を持っていることを感じます。本人が「オレはもうだめになってしまった」と考えたり、ご家族が「おじいちゃんは壊れちゃった。昔のおじいちゃんではない」と、とらえたりすることがあるのです。
前回もお話ししましたが、機能が低下していくのはその方の人生の一部です。その事実を含めて、ご家族が最期まで一緒に暮らし、これで良かったと思える状況をつくっていくことが大切です。ここに心理士の方のサポートが必要だと考えています。
― 終末期や障害の受容と同じプロセスですね。
佐々木 そうですね。ただ、認知症が他の病気や障害と違うのは、90歳を過ぎればほぼ全員が認知症かその予備軍(軽度認知障害)になるのですから、誰もが長生きすれば認知症を避けられないということです。実はそれがまだ多くの方に理解されていません。
おじいちゃんが認知症になり、おばあちゃんがなり、息子さんもお嫁さんもなり、いずれわれわれもなる。そういう病気ですから、人間が生きるとはこういうものだよねと、ちゃんと伝えていかなくてはなりません。
現代医療では、健常に近づくことが「善」であるかのような価値観ばかりが刷り込まれています。認知症になったこのおじいちゃんを医者はどうやって治してくれるのかと求めるのではなく、認知症があってもおじいちゃんはおじいちゃんだということを受け入れていく。そのためのサポートが求められているのです。
受容のプロセスのサポートという点では看取りに通底するものがあると思います。認知症の受容に関しても、われわれ医師や看護師にはなかなかサポートするのが難しい。理屈はわかっていても、具体的な援助ができない専門職は多いのです。そこに心理士の方が関わってもらえるなら、それはとてもありがたいことです。
― 認知症だけでなく、がんなども、本人だけでなくご家族が、親やパートナーなど大切な人が病気になった事実を受け入れられないこともありますね。
佐々木 本人もご家族も苦しんでいる。でも、何に苦しんでいるのかわからないこともけっこう多いですね。病気になった運命を受け入れたいのに諦めきれないとか、お母さんがもう助からないことがつらいとか。治らない病気そのもので苦しんでいるのではなく、病気の受容のプロセスの中でつまずいているのです。そこで、自分が何に苦しんでいるのかをまず明らかにする。そこに気づくことができれば、自分で立ち上がれる人は多いと思います。
それは、われわれが「あなたはここにつまずいているのですよ」と言っても、スッと受け入れられるものではありません。対話を繰り返す中で、「あ、ここなのかもしれない」と本人が気づけば、きっと変われます。そういう対話の時間、考える時間が必要ですし、本人が気づき、変われるようサポートすることがとても重要です。
― そうしたことに心理士が関われればと思いますが、現在の医療や介護の制度では心理士への報酬が限られていて、実際にはなかなか雇用していただくのが難しい状況です。
佐々木 心理士の方がもし地域に出てきてくださるなら、採算をトータルで見れば雇用できると思います。在宅医療では報酬で評価されていない専門職は、実は多いのです。例えば当法人では診療には看護師に同行してもらっていますが、これは訪問看護ではないので報酬はつきません。訪問車両のドライバーもソーシャルワーカーも制度上報酬はありません。報酬がついている管理栄養士にしても、自分で稼げる点数だけでは赤字です。それでも必要だから雇用していますし、雇用することで患者さんたちにより付加価値のある在宅ケアが提供できると考えています。
例えば心理士の方にも診療に同行してもらって、医学的な部分を医師が見て、心理士の方にはスピリチュアルケアを担当していただく。時には医師が引き上げたあとも残って話をするというようなことをときどきやっていただくだけでも、とても付加価値が高いと思います。
― 在宅での心理支援を志している心理士にとっては非常にうれしいお話です。今後、在宅で心理士が活躍していくためにはどんな資質や視点が求められているでしょうか。
佐々木 在宅ではさまざまな職種、事業体が連携して患者さんの支援に当たります。ですから、多職種連携をスムーズに進められることは重要です。また、入院と違って在宅はいろいろな社会サービスをつなぎ合わせて使うことが多いので、介護保険や難病、障害などの制度についての知識を身につけることは必要になってくると思います。
僕は在宅医療をするようになって、患者さんの生活を支える上で医療ができることはほんのわずかだということを痛感しました。専門職は専門性を身につけるほど、専門性の枠の中で満点を目指したくなりますが、在宅では、周囲に目を向けて、どんなフィールドが広がっているのか、そこにどんな課題があるのかを把握しておく必要があります。すべてのフィールドの専門家である必要はありません。しかし、全体図を把握しておくこと。そして、自分はその中のこの分野のエキスパートだが、あの分野なら誰をガイドに付ければいいかをガイダンスできるようにしておくこと。そんな意識、関心を持つことは大切だと思います。
― 多職種協働の意識と広い視野が必要だということですね。ありがとうございました。
★前編の記事はこちら
(インタビュー・文:介護福祉ライター/公認心理師・臨床心理士・社会福祉士 宮下公美子)
佐々木 淳 Jun Sasaki
医療法人社団悠翔会 理事長・診療部長
― 前回挙げてくださった「看取り」のほかに、在宅では、認知症がある人にも心理的サポートが求められているとのことですが、心理士にどのような役割を期待されていますか。
佐々木 「認知症」という呼称は誰もが知るようになりましたが、「認知症」についての正しい知識と理解はまだまだ広がっていません。特に、本人やご家族が偏見を持っていることを感じます。本人が「オレはもうだめになってしまった」と考えたり、ご家族が「おじいちゃんは壊れちゃった。昔のおじいちゃんではない」と、とらえたりすることがあるのです。
前回もお話ししましたが、機能が低下していくのはその方の人生の一部です。その事実を含めて、ご家族が最期まで一緒に暮らし、これで良かったと思える状況をつくっていくことが大切です。ここに心理士の方のサポートが必要だと考えています。
― 終末期や障害の受容と同じプロセスですね。
佐々木 そうですね。ただ、認知症が他の病気や障害と違うのは、90歳を過ぎればほぼ全員が認知症かその予備軍(軽度認知障害)になるのですから、誰もが長生きすれば認知症を避けられないということです。実はそれがまだ多くの方に理解されていません。
おじいちゃんが認知症になり、おばあちゃんがなり、息子さんもお嫁さんもなり、いずれわれわれもなる。そういう病気ですから、人間が生きるとはこういうものだよねと、ちゃんと伝えていかなくてはなりません。
現代医療では、健常に近づくことが「善」であるかのような価値観ばかりが刷り込まれています。認知症になったこのおじいちゃんを医者はどうやって治してくれるのかと求めるのではなく、認知症があってもおじいちゃんはおじいちゃんだということを受け入れていく。そのためのサポートが求められているのです。
受容のプロセスのサポートという点では看取りに通底するものがあると思います。認知症の受容に関しても、われわれ医師や看護師にはなかなかサポートするのが難しい。理屈はわかっていても、具体的な援助ができない専門職は多いのです。そこに心理士の方が関わってもらえるなら、それはとてもありがたいことです。
― 認知症だけでなく、がんなども、本人だけでなくご家族が、親やパートナーなど大切な人が病気になった事実を受け入れられないこともありますね。
佐々木 本人もご家族も苦しんでいる。でも、何に苦しんでいるのかわからないこともけっこう多いですね。病気になった運命を受け入れたいのに諦めきれないとか、お母さんがもう助からないことがつらいとか。治らない病気そのもので苦しんでいるのではなく、病気の受容のプロセスの中でつまずいているのです。そこで、自分が何に苦しんでいるのかをまず明らかにする。そこに気づくことができれば、自分で立ち上がれる人は多いと思います。
それは、われわれが「あなたはここにつまずいているのですよ」と言っても、スッと受け入れられるものではありません。対話を繰り返す中で、「あ、ここなのかもしれない」と本人が気づけば、きっと変われます。そういう対話の時間、考える時間が必要ですし、本人が気づき、変われるようサポートすることがとても重要です。
― そうしたことに心理士が関われればと思いますが、現在の医療や介護の制度では心理士への報酬が限られていて、実際にはなかなか雇用していただくのが難しい状況です。
佐々木 心理士の方がもし地域に出てきてくださるなら、採算をトータルで見れば雇用できると思います。在宅医療では報酬で評価されていない専門職は、実は多いのです。例えば当法人では診療には看護師に同行してもらっていますが、これは訪問看護ではないので報酬はつきません。訪問車両のドライバーもソーシャルワーカーも制度上報酬はありません。報酬がついている管理栄養士にしても、自分で稼げる点数だけでは赤字です。それでも必要だから雇用していますし、雇用することで患者さんたちにより付加価値のある在宅ケアが提供できると考えています。
例えば心理士の方にも診療に同行してもらって、医学的な部分を医師が見て、心理士の方にはスピリチュアルケアを担当していただく。時には医師が引き上げたあとも残って話をするというようなことをときどきやっていただくだけでも、とても付加価値が高いと思います。
― 在宅での心理支援を志している心理士にとっては非常にうれしいお話です。今後、在宅で心理士が活躍していくためにはどんな資質や視点が求められているでしょうか。
佐々木 在宅ではさまざまな職種、事業体が連携して患者さんの支援に当たります。ですから、多職種連携をスムーズに進められることは重要です。また、入院と違って在宅はいろいろな社会サービスをつなぎ合わせて使うことが多いので、介護保険や難病、障害などの制度についての知識を身につけることは必要になってくると思います。
僕は在宅医療をするようになって、患者さんの生活を支える上で医療ができることはほんのわずかだということを痛感しました。専門職は専門性を身につけるほど、専門性の枠の中で満点を目指したくなりますが、在宅では、周囲に目を向けて、どんなフィールドが広がっているのか、そこにどんな課題があるのかを把握しておく必要があります。すべてのフィールドの専門家である必要はありません。しかし、全体図を把握しておくこと。そして、自分はその中のこの分野のエキスパートだが、あの分野なら誰をガイドに付ければいいかをガイダンスできるようにしておくこと。そんな意識、関心を持つことは大切だと思います。
― 多職種協働の意識と広い視野が必要だということですね。ありがとうございました。
★前編の記事はこちら
(インタビュー・文:介護福祉ライター/公認心理師・臨床心理士・社会福祉士 宮下公美子)
佐々木 淳 Jun Sasaki
医療法人社団悠翔会 理事長・診療部長

2006年に33歳で在宅医療に特化したクリニックを開設し、2021年10月現在、首都圏を中心に18拠点を運営。最期まで自分の人生の主人公として生きられる医療の実現を目指して在宅医療に取り組む。2021年8月には自宅療養する新型コロナウイルス患者の診療チームを編成し、自身も既存患者と並行して訪問。